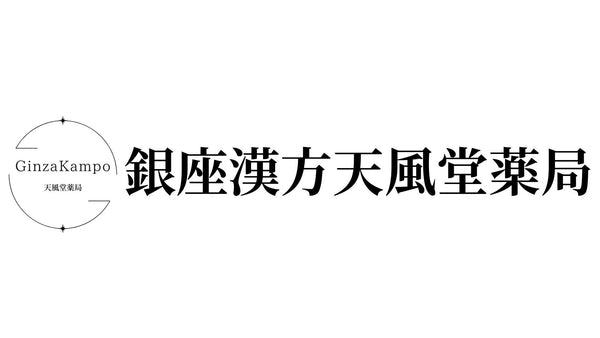Colomn
お知らせ
更年期と美容の変化 | 内側から輝きを保つ漢方アプローチ【専門家監修】
「肌のハリや潤いが減った」「髪にコシがなくなった」「シミやシワが気になるようになった」…更年期を迎えると、こうした見た目の変化に戸惑う方も少なくありません。鏡を見るたびに「以前と違う」と感じることが増えていませんか? 本記事では、東洋医学の視点から更年期の美容変化の特徴と、体質に合わせた内側からのケア方法について解説します。自分でできる養生法から、専門家に相談するメリットまでご紹介します。 更年期の美容変化と東洋医学的な考え方 更年期に肌や髪に変化が起きるメカニズム 更年期の美容変化は、西洋医学では女性ホルモン(エストロゲン)の減少が肌のコラーゲン生成や皮脂分泌、毛髪の成長サイクルに影響を与えることで起こると考えられています。エストロゲンは肌の弾力やハリ、潤いを保つ重要な役割を担っているため、その減少は見た目にも影響します。 一方、東洋医学では「気・血・水」のバランスという観点から美容を捉えます。特に「血」と「津液(しんえき)」という体内の潤いを表す概念が重要とされます。また、「腎(じん)」の働きも髪の艶やハリに関わると考えられています。 東洋医学では「美は内側から」という考え方があり、見た目の変化は内側の状態を映し出していると捉えます。そのため、表面的なケアだけでなく、体内のバランスを整えることを重視します。 体質と美容変化の関連性 東洋医学では、美容変化の特徴も体質によって違いがあると考えます。以下に代表的な体質傾向と美容変化の特徴をご紹介します。(あくまで一般的な傾向であり、個人差があります) 血虚(けっきょ)傾向の方の美容変化 肌が乾燥しやすく、くすみやすい 爪が割れやすく、髪にハリがない 唇の色が薄く、肌の血色が悪い 肌の回復力が弱く、傷が治りにくい 陰虚(いんきょ)傾向の方の美容変化 肌がカサカサして内側から乾燥している感じ ほてりを感じやすく、頬が赤くなることも 髪が乾燥しパサつきやすい のどや目の乾燥感を伴うことも 腎虚(じんきょ)傾向の方の美容変化 髪の老化(白髪、抜け毛など)が進みやすい 顔色が暗く、くすみやすい 歯や骨の弱さを感じることも 疲れが顔に出やすい 気滞(きたい)傾向の方の美容変化 ストレスで肌荒れしやすい 顔の一部(特にアゴ周り)にニキビができやすい むくみやすく、顔の輪郭がぼやけやすい 表情筋の緊張からシワができやすい これらの体質傾向は混在することもあり、また生活習慣や季節によっても変化します。体質の傾向を知ることで、より自分に合った対応が見えてくることがあります。...
更年期と美容の変化 | 内側から輝きを保つ漢方アプローチ【専門家監修】
「肌のハリや潤いが減った」「髪にコシがなくなった」「シミやシワが気になるようになった」…更年期を迎えると、こうした見た目の変化に戸惑う方も少なくありません。鏡を見るたびに「以前と違う」と感じることが増えていませんか? 本記事では、東洋医学の視点から更年期の美容変化の特徴と、体質に合わせた内側からのケア方法について解説します。自分でできる養生法から、専門家に相談するメリットまでご紹介します。 更年期の美容変化と東洋医学的な考え方 更年期に肌や髪に変化が起きるメカニズム 更年期の美容変化は、西洋医学では女性ホルモン(エストロゲン)の減少が肌のコラーゲン生成や皮脂分泌、毛髪の成長サイクルに影響を与えることで起こると考えられています。エストロゲンは肌の弾力やハリ、潤いを保つ重要な役割を担っているため、その減少は見た目にも影響します。 一方、東洋医学では「気・血・水」のバランスという観点から美容を捉えます。特に「血」と「津液(しんえき)」という体内の潤いを表す概念が重要とされます。また、「腎(じん)」の働きも髪の艶やハリに関わると考えられています。 東洋医学では「美は内側から」という考え方があり、見た目の変化は内側の状態を映し出していると捉えます。そのため、表面的なケアだけでなく、体内のバランスを整えることを重視します。 体質と美容変化の関連性 東洋医学では、美容変化の特徴も体質によって違いがあると考えます。以下に代表的な体質傾向と美容変化の特徴をご紹介します。(あくまで一般的な傾向であり、個人差があります) 血虚(けっきょ)傾向の方の美容変化 肌が乾燥しやすく、くすみやすい 爪が割れやすく、髪にハリがない 唇の色が薄く、肌の血色が悪い 肌の回復力が弱く、傷が治りにくい 陰虚(いんきょ)傾向の方の美容変化 肌がカサカサして内側から乾燥している感じ ほてりを感じやすく、頬が赤くなることも 髪が乾燥しパサつきやすい のどや目の乾燥感を伴うことも 腎虚(じんきょ)傾向の方の美容変化 髪の老化(白髪、抜け毛など)が進みやすい 顔色が暗く、くすみやすい 歯や骨の弱さを感じることも 疲れが顔に出やすい 気滞(きたい)傾向の方の美容変化 ストレスで肌荒れしやすい 顔の一部(特にアゴ周り)にニキビができやすい むくみやすく、顔の輪郭がぼやけやすい 表情筋の緊張からシワができやすい これらの体質傾向は混在することもあり、また生活習慣や季節によっても変化します。体質の傾向を知ることで、より自分に合った対応が見えてくることがあります。...
更年期と疲れやすさ | 活力を高める漢方アプローチ【専門家監修】
「以前なら平気だった家事や仕事でも疲れやすくなった」「午後になると急に体が重くなる」「朝起きても疲れが取れていない」…更年期を迎えると、こうした疲労感に悩まされる方が少なくありません。「なぜこんなに疲れるのだろう」と戸惑っている方も多いのではないでしょうか。 本記事では、東洋医学の視点から更年期の疲れやすさの特徴と、体質に合わせた活力を高める方法について解説します。自分でできる養生法から、専門家に相談するメリットまでご紹介します。 更年期の疲れやすさと東洋医学的な考え方 更年期に疲労感が増すメカニズム 更年期の疲れやすさは、西洋医学では女性ホルモンの減少が自律神経系や代謝に影響を与え、体のエネルギー産生や回復機能が低下することで起こると考えられています。また、更年期に伴う睡眠の質の低下も疲労感に影響します。 一方、東洋医学では「気・血・水」のバランスという観点から疲労を捉えます。特に「気」と「腎(じん)」の働きが重要とされます。東洋医学における「気」はエネルギーや活力の源、「腎」は生命力の根本を司る臓腑と考えられています。 東洋医学では「形は気を載せ、気は形を生ず」という考え方があり、目に見えない「気」の状態が身体の状態に大きく影響すると考えます。また、「腎は先天の本(せんてんのもと)」といわれ、年齢を重ねるにつれて腎の働きが徐々に弱まることで、様々な変化が起こると考えられています。 体質と疲労パターンの関連性 東洋医学では、疲れやすさの特徴も体質によって違いがあると考えます。以下に代表的な体質傾向と疲労の特徴をご紹介します。(あくまで一般的な傾向であり、個人差があります) 気虚(ききょ)傾向の方の疲労 少し動くだけでも疲れを感じる 声が小さく、話すのも疲れる 汗をかきやすく、風邪をひきやすい 午後に特に疲れを感じることが多い 血虚(けっきょ)傾向の方の疲労 じっとしていても目の疲れや頭の重さを感じる めまいやふらつきを伴うことがある 顔色が青白く、唇の色が薄い 爪が割れやすく、肌が乾燥する 腎虚(じんきょ)傾向の方の疲労 腰や膝の力が入りにくい 疲れが翌日まで残りやすい 寝起きが悪く、朝の活動開始に時間がかかる 耳鳴りや頭髪の変化を伴うことも 気滞(きたい)傾向の方の疲労 精神的なストレスで疲労感が増す 胸や脇の張りを感じる ため息が出やすい 気分の波があり、イライラすると疲れを強く感じる これらの体質傾向は混在することもあり、また生活習慣や季節によっても変化します。体質の傾向を知ることで、より自分に合った対応が見えてくることがあります。...
更年期と疲れやすさ | 活力を高める漢方アプローチ【専門家監修】
「以前なら平気だった家事や仕事でも疲れやすくなった」「午後になると急に体が重くなる」「朝起きても疲れが取れていない」…更年期を迎えると、こうした疲労感に悩まされる方が少なくありません。「なぜこんなに疲れるのだろう」と戸惑っている方も多いのではないでしょうか。 本記事では、東洋医学の視点から更年期の疲れやすさの特徴と、体質に合わせた活力を高める方法について解説します。自分でできる養生法から、専門家に相談するメリットまでご紹介します。 更年期の疲れやすさと東洋医学的な考え方 更年期に疲労感が増すメカニズム 更年期の疲れやすさは、西洋医学では女性ホルモンの減少が自律神経系や代謝に影響を与え、体のエネルギー産生や回復機能が低下することで起こると考えられています。また、更年期に伴う睡眠の質の低下も疲労感に影響します。 一方、東洋医学では「気・血・水」のバランスという観点から疲労を捉えます。特に「気」と「腎(じん)」の働きが重要とされます。東洋医学における「気」はエネルギーや活力の源、「腎」は生命力の根本を司る臓腑と考えられています。 東洋医学では「形は気を載せ、気は形を生ず」という考え方があり、目に見えない「気」の状態が身体の状態に大きく影響すると考えます。また、「腎は先天の本(せんてんのもと)」といわれ、年齢を重ねるにつれて腎の働きが徐々に弱まることで、様々な変化が起こると考えられています。 体質と疲労パターンの関連性 東洋医学では、疲れやすさの特徴も体質によって違いがあると考えます。以下に代表的な体質傾向と疲労の特徴をご紹介します。(あくまで一般的な傾向であり、個人差があります) 気虚(ききょ)傾向の方の疲労 少し動くだけでも疲れを感じる 声が小さく、話すのも疲れる 汗をかきやすく、風邪をひきやすい 午後に特に疲れを感じることが多い 血虚(けっきょ)傾向の方の疲労 じっとしていても目の疲れや頭の重さを感じる めまいやふらつきを伴うことがある 顔色が青白く、唇の色が薄い 爪が割れやすく、肌が乾燥する 腎虚(じんきょ)傾向の方の疲労 腰や膝の力が入りにくい 疲れが翌日まで残りやすい 寝起きが悪く、朝の活動開始に時間がかかる 耳鳴りや頭髪の変化を伴うことも 気滞(きたい)傾向の方の疲労 精神的なストレスで疲労感が増す 胸や脇の張りを感じる ため息が出やすい 気分の波があり、イライラすると疲れを強く感じる これらの体質傾向は混在することもあり、また生活習慣や季節によっても変化します。体質の傾向を知ることで、より自分に合った対応が見えてくることがあります。...
更年期と冷え | 体を芯から温める漢方アプローチ【専門家監修】
「冬だけでなく、夏でも手足が冷える」「温かい部屋でも足先が冷たい」「温めても芯から温まった感じがしない」…更年期に入ってから、こうした冷えの悩みが増えていませんか?ホットフラッシュとは反対に、体の末端の冷えを感じる方も少なくありません。 本記事では、東洋医学の視点から更年期の冷えの特徴と、体質に合わせた漢方的アプローチについて解説します。自分でできる温め方から、専門家に相談するメリットまでご紹介します。 更年期の冷えと東洋医学的な考え方 更年期に冷えが生じるメカニズム 更年期の冷えは、西洋医学では女性ホルモンの減少によって血行が悪くなったり、自律神経のバランスが乱れることで起こると考えられています。特に手足など末端部分の血流が滞りやすくなり、冷えを感じやすくなります。 一方、東洋医学では「気・血・水」のバランスという観点から冷えを捉えます。特に「気」と「血」の巡りが滞ったり、「陽気」と呼ばれる体を温める力が弱まったりすることで、冷えが生じると考えます。 東洋医学では「冷えは万病の元」と言われるほど、体の冷えは様々な不調の原因になると考えられています。冷えのタイプや部位から体の状態を読み取り、根本的なバランスを整えるアプローチを大切にしています。 体質と冷えパターンの関連性 東洋医学では、冷えの特徴も体質によって違いがあると考えます。以下に代表的な体質傾向と冷えの特徴をご紹介します。(あくまで一般的な傾向であり、個人差があります) 気虚(ききょ)傾向の方の冷え 全身的に力が入りにくく、体が温まりにくい 疲れやすく、動くとしんどい 声が小さく、話すのも疲れる 汗をかきやすく、風邪をひきやすい 血虚(けっきょ)傾向の方の冷え 手足の先が特に冷えやすい 顔色が青白く、唇や爪の色が薄い 肌が乾燥しやすい めまいや動悸を感じることも 陽虚(ようきょ)傾向の方の冷え お腹や背中、腰など体の芯が冷える感じ 温かいものを好み、寒さに弱い 水分をとると余計に冷える感じがする 朝起きるのがつらい 瘀血(おけつ)傾向の方の冷え 局所的に冷えや痛みを感じる 皮膚に内出血ができやすい 肌の血色が悪く、シミができやすい 生理痛が強かった、または不順だった これらの体質傾向は混在することもあり、また生活習慣や季節によっても変化します。体質の傾向を知ることで、より自分に合った対応が見えてくることがあります。...
更年期と冷え | 体を芯から温める漢方アプローチ【専門家監修】
「冬だけでなく、夏でも手足が冷える」「温かい部屋でも足先が冷たい」「温めても芯から温まった感じがしない」…更年期に入ってから、こうした冷えの悩みが増えていませんか?ホットフラッシュとは反対に、体の末端の冷えを感じる方も少なくありません。 本記事では、東洋医学の視点から更年期の冷えの特徴と、体質に合わせた漢方的アプローチについて解説します。自分でできる温め方から、専門家に相談するメリットまでご紹介します。 更年期の冷えと東洋医学的な考え方 更年期に冷えが生じるメカニズム 更年期の冷えは、西洋医学では女性ホルモンの減少によって血行が悪くなったり、自律神経のバランスが乱れることで起こると考えられています。特に手足など末端部分の血流が滞りやすくなり、冷えを感じやすくなります。 一方、東洋医学では「気・血・水」のバランスという観点から冷えを捉えます。特に「気」と「血」の巡りが滞ったり、「陽気」と呼ばれる体を温める力が弱まったりすることで、冷えが生じると考えます。 東洋医学では「冷えは万病の元」と言われるほど、体の冷えは様々な不調の原因になると考えられています。冷えのタイプや部位から体の状態を読み取り、根本的なバランスを整えるアプローチを大切にしています。 体質と冷えパターンの関連性 東洋医学では、冷えの特徴も体質によって違いがあると考えます。以下に代表的な体質傾向と冷えの特徴をご紹介します。(あくまで一般的な傾向であり、個人差があります) 気虚(ききょ)傾向の方の冷え 全身的に力が入りにくく、体が温まりにくい 疲れやすく、動くとしんどい 声が小さく、話すのも疲れる 汗をかきやすく、風邪をひきやすい 血虚(けっきょ)傾向の方の冷え 手足の先が特に冷えやすい 顔色が青白く、唇や爪の色が薄い 肌が乾燥しやすい めまいや動悸を感じることも 陽虚(ようきょ)傾向の方の冷え お腹や背中、腰など体の芯が冷える感じ 温かいものを好み、寒さに弱い 水分をとると余計に冷える感じがする 朝起きるのがつらい 瘀血(おけつ)傾向の方の冷え 局所的に冷えや痛みを感じる 皮膚に内出血ができやすい 肌の血色が悪く、シミができやすい 生理痛が強かった、または不順だった これらの体質傾向は混在することもあり、また生活習慣や季節によっても変化します。体質の傾向を知ることで、より自分に合った対応が見えてくることがあります。...
更年期と気分の変化 | 心のバランスを整える漢方アプローチ【専門家監修】
突然涙が出てきたり、些細なことでイライラしたり、気分の波を感じることが増えていませんか?更年期を迎えると、身体的な変化だけでなく、心の状態にも変化が現れることがあります。「なぜこんなに感情が不安定になるのだろう」と戸惑っている方も多いのではないでしょうか。 本記事では、東洋医学の視点から更年期に起こる気分の変化の特徴と、体質に合わせた和らげ方について解説します。自分でできる心のセルフケアから、専門家に相談するメリットまでご紹介します。 更年期の気分変化と東洋医学的な考え方 更年期に心のバランスが変化するメカニズム 更年期の気分変化は、西洋医学では女性ホルモン(エストロゲン)の減少が脳内の神経伝達物質(セロトニンやドーパミンなど)のバランスに影響を与えることで起こると考えられています。 一方、東洋医学では「気・血・水」のバランスという観点から心の状態を捉えます。特に「肝(かん)」と呼ばれる機能が重要とされます。東洋医学における「肝」は、西洋医学の肝臓とは異なり、気の巡りや感情のバランスを調整する働きを担っていると考えられています。 東洋医学では「心身一如」という考え方があり、心と体は互いに密接に影響し合うと考えます。更年期に起こる身体変化が心に影響し、また心の状態が体にも影響するという相互関係の中で、気分の変化を捉えていきます。 体質と気分変化の関連性 東洋医学では、気分の変化の特徴も体質によって違いがあると考えます。以下に代表的な体質傾向の特徴をご紹介します。(あくまで一般的な傾向であり、個人差があります) 肝気鬱結(かんきうっけつ)傾向の方 イライラしやすく、気分の波が大きい 胸や脇腹に詰まった感じがすることも ため息が出やすい ストレスに敏感で、緊張しやすい 肝陽上亢(かんようじょうこう)傾向の方 怒りっぽく、頭に血が上る感じがする 頭痛や目の充血を伴うことも 顔が熱くなりやすい 口が渇きやすい 心脾両虚(しんぴりょうきょ)傾向の方 憂うつ感や不安感が強い 疲れやすく、気力が出にくい 食欲不振や消化不良を伴うことも 考え事が多くなり、眠りが浅くなる これらの体質傾向は混在することもあり、また生活習慣や季節によっても変化します。体質の傾向を知ることで、より自分に合った対応が見えてくることがあります。 体質別の心を整える養生法 気分の変化の特徴や体質によって、日常生活での工夫の仕方も変わってきます。自分の体質傾向に合わせた養生法の考え方をご紹介します。 肝気鬱結(かんきうっけつ)傾向の方の養生法 気の巡りが滞り、イライラしやすい方は、気の流れを促すアプローチが基本となります。 食生活での工夫...
更年期と気分の変化 | 心のバランスを整える漢方アプローチ【専門家監修】
突然涙が出てきたり、些細なことでイライラしたり、気分の波を感じることが増えていませんか?更年期を迎えると、身体的な変化だけでなく、心の状態にも変化が現れることがあります。「なぜこんなに感情が不安定になるのだろう」と戸惑っている方も多いのではないでしょうか。 本記事では、東洋医学の視点から更年期に起こる気分の変化の特徴と、体質に合わせた和らげ方について解説します。自分でできる心のセルフケアから、専門家に相談するメリットまでご紹介します。 更年期の気分変化と東洋医学的な考え方 更年期に心のバランスが変化するメカニズム 更年期の気分変化は、西洋医学では女性ホルモン(エストロゲン)の減少が脳内の神経伝達物質(セロトニンやドーパミンなど)のバランスに影響を与えることで起こると考えられています。 一方、東洋医学では「気・血・水」のバランスという観点から心の状態を捉えます。特に「肝(かん)」と呼ばれる機能が重要とされます。東洋医学における「肝」は、西洋医学の肝臓とは異なり、気の巡りや感情のバランスを調整する働きを担っていると考えられています。 東洋医学では「心身一如」という考え方があり、心と体は互いに密接に影響し合うと考えます。更年期に起こる身体変化が心に影響し、また心の状態が体にも影響するという相互関係の中で、気分の変化を捉えていきます。 体質と気分変化の関連性 東洋医学では、気分の変化の特徴も体質によって違いがあると考えます。以下に代表的な体質傾向の特徴をご紹介します。(あくまで一般的な傾向であり、個人差があります) 肝気鬱結(かんきうっけつ)傾向の方 イライラしやすく、気分の波が大きい 胸や脇腹に詰まった感じがすることも ため息が出やすい ストレスに敏感で、緊張しやすい 肝陽上亢(かんようじょうこう)傾向の方 怒りっぽく、頭に血が上る感じがする 頭痛や目の充血を伴うことも 顔が熱くなりやすい 口が渇きやすい 心脾両虚(しんぴりょうきょ)傾向の方 憂うつ感や不安感が強い 疲れやすく、気力が出にくい 食欲不振や消化不良を伴うことも 考え事が多くなり、眠りが浅くなる これらの体質傾向は混在することもあり、また生活習慣や季節によっても変化します。体質の傾向を知ることで、より自分に合った対応が見えてくることがあります。 体質別の心を整える養生法 気分の変化の特徴や体質によって、日常生活での工夫の仕方も変わってきます。自分の体質傾向に合わせた養生法の考え方をご紹介します。 肝気鬱結(かんきうっけつ)傾向の方の養生法 気の巡りが滞り、イライラしやすい方は、気の流れを促すアプローチが基本となります。 食生活での工夫...
更年期と不眠 | 眠りの質を高める漢方アプローチ【専門家監修】
なかなか寝付けない、夜中に何度も目が覚める、朝早く目覚めてしまう—更年期に入ってから、こうした睡眠の悩みを抱える方は少なくありません。昼間の疲れを感じているのに、夜になると目が冴えてしまうというジレンマに悩まされていませんか? 本記事では、東洋医学の視点から更年期の不眠の特徴と、体質に合わせた漢方的アプローチについて解説します。自分でできる養生法から、専門家に相談するメリットまでご紹介します。 更年期の不眠と東洋医学的な考え方 更年期に睡眠の質が変化するメカニズム 更年期の不眠は、西洋医学では女性ホルモンの減少が自律神経系に影響を与え、体温調節機能や心身のリズムが乱れることで起こると考えられています。ほてりや発汗といった身体症状が睡眠を妨げることもあります。 一方、東洋医学では「気・血・水」のバランスという観点から睡眠の質を捉えます。特に「心(しん)」と呼ばれる心と身体の状態を司る機能と、「腎(じん)」と呼ばれる生命エネルギーを蓄える機能のバランスが重要と考えます。 東洋医学では「眠りは心身の状態を映す鏡」と考え、不眠の現れ方から体の状態を読み取ります。同じ不眠でも、寝付きの悪さ、中途覚醒、早朝覚醒など、症状の特徴から体質の傾向を考えていきます。 体質と不眠パターンの関連性 東洋医学では、不眠の特徴も体質によって違いがあると考えます。以下に代表的な体質傾向と不眠パターンの特徴をご紹介します。(あくまで一般的な傾向であり、個人差があります) 心の熱(心火)が強い傾向の方 なかなか寝付けないタイプの不眠 頭がさえて考え事が続く 胸がドキドキしたり、熱感を感じることも 口の渇きを伴うことも 気の巡りが滞る傾向の方 眠りが浅く、夢をよく見るタイプの不眠 胸や脇腹の張りや不快感を感じることも ため息が出やすい 食後に眠気を感じることも 腎(じん)の働きが弱い傾向の方 早朝に目が覚めてしまうタイプの不眠 疲れやすく、腰や膝に力が入りにくい 耳鳴りや目の乾燥感を伴うことも 夜間のトイレが増えることも これらの体質傾向は混在することもあり、また生活習慣や季節によっても変化します。体質の傾向を知ることで、より自分に合った対応が見えてくることがあります。 体質別の睡眠を整える養生法 不眠の特徴や体質によって、日常生活での工夫の仕方も変わってきます。自分の体質傾向に合わせた養生法の考え方をご紹介します。 心の熱(心火)が強い傾向の方の養生法 頭がさえて寝付きにくい方は、心を落ち着かせるアプローチが基本となります。 食生活での工夫...
更年期と不眠 | 眠りの質を高める漢方アプローチ【専門家監修】
なかなか寝付けない、夜中に何度も目が覚める、朝早く目覚めてしまう—更年期に入ってから、こうした睡眠の悩みを抱える方は少なくありません。昼間の疲れを感じているのに、夜になると目が冴えてしまうというジレンマに悩まされていませんか? 本記事では、東洋医学の視点から更年期の不眠の特徴と、体質に合わせた漢方的アプローチについて解説します。自分でできる養生法から、専門家に相談するメリットまでご紹介します。 更年期の不眠と東洋医学的な考え方 更年期に睡眠の質が変化するメカニズム 更年期の不眠は、西洋医学では女性ホルモンの減少が自律神経系に影響を与え、体温調節機能や心身のリズムが乱れることで起こると考えられています。ほてりや発汗といった身体症状が睡眠を妨げることもあります。 一方、東洋医学では「気・血・水」のバランスという観点から睡眠の質を捉えます。特に「心(しん)」と呼ばれる心と身体の状態を司る機能と、「腎(じん)」と呼ばれる生命エネルギーを蓄える機能のバランスが重要と考えます。 東洋医学では「眠りは心身の状態を映す鏡」と考え、不眠の現れ方から体の状態を読み取ります。同じ不眠でも、寝付きの悪さ、中途覚醒、早朝覚醒など、症状の特徴から体質の傾向を考えていきます。 体質と不眠パターンの関連性 東洋医学では、不眠の特徴も体質によって違いがあると考えます。以下に代表的な体質傾向と不眠パターンの特徴をご紹介します。(あくまで一般的な傾向であり、個人差があります) 心の熱(心火)が強い傾向の方 なかなか寝付けないタイプの不眠 頭がさえて考え事が続く 胸がドキドキしたり、熱感を感じることも 口の渇きを伴うことも 気の巡りが滞る傾向の方 眠りが浅く、夢をよく見るタイプの不眠 胸や脇腹の張りや不快感を感じることも ため息が出やすい 食後に眠気を感じることも 腎(じん)の働きが弱い傾向の方 早朝に目が覚めてしまうタイプの不眠 疲れやすく、腰や膝に力が入りにくい 耳鳴りや目の乾燥感を伴うことも 夜間のトイレが増えることも これらの体質傾向は混在することもあり、また生活習慣や季節によっても変化します。体質の傾向を知ることで、より自分に合った対応が見えてくることがあります。 体質別の睡眠を整える養生法 不眠の特徴や体質によって、日常生活での工夫の仕方も変わってきます。自分の体質傾向に合わせた養生法の考え方をご紹介します。 心の熱(心火)が強い傾向の方の養生法 頭がさえて寝付きにくい方は、心を落ち着かせるアプローチが基本となります。 食生活での工夫...
更年期のほてりと漢方 | 体質から考える和らげ方【専門家監修】
会議中に突然、顔がカッと熱くなり、汗が噴き出してくる―そんな経験はありませんか? 周囲に気づかれないよう必死でやり過ごしている方も多いのではないでしょうか。 本記事では、東洋医学の視点から更年期に起こるほてりの特徴と、体質に合わせた和らげ方について解説します。自分でできるセルフケアから、専門家に相談するメリットまでご紹介します。 更年期のほてりについての東洋医学的な考え方 ほてりが起こるメカニズム 更年期のほてりは、西洋医学では女性ホルモン(エストロゲン)の減少により、体温を調節する自律神経のバランスが乱れることで起こると考えられています。 一方、東洋医学では「気・血・水」のバランスという観点から捉えます。特に「気」の流れが乱れたり、「陰」の力が弱まったりすることで、体内の熱のバランスが崩れている状態と考えるのが特徴です。 東洋医学では「一人ひとりの体質や生活環境によって、同じほてりでも現れ方や特徴が異なる」という考え方をします。そのため、体質に合わせたアプローチが大切にされています。 体質との関連性 東洋医学では、ほてりの特徴も体質によって違いがあると考えます。以下に代表的な体質傾向の特徴をご紹介します。(あくまで一般的な傾向であり、個人差があります) 熱証傾向の方のほてり 顔が赤くなりやすい 熱感が強く、汗もたくさん出る傾向 口の渇きや喉の乾燥を伴うことも 温かい場所や飲食物で悪化しやすい 陰虚傾向の方のほてり 特に午後から夕方にかけて症状が出やすい ほてりの後に疲れを感じやすい 手のひらや足の裏などにも熱感を感じることも 乾燥感や軽い不眠を伴うことも 気逆傾向の方のほてり 突然上半身に熱が上がってくる感覚 ストレスや緊張で悪化しやすい 胸のつかえ感を伴うことも 落ち着いた環境では比較的おさまりやすい これらの体質傾向は混在することもあり、また生活習慣や季節によっても変化します。体質の傾向を知ることで、より自分に合った対応が見えてくることがあります。 体質別のセルフケアの考え方 ほてりを感じる際、体質の傾向によって日常生活での工夫の仕方も変わってきます。自分の体質傾向に合わせたセルフケアの考え方をご紹介します。 熱証傾向の方のセルフケア 体内の熱が強い傾向にある方は、熱を冷ますアプローチが基本となります。...
更年期のほてりと漢方 | 体質から考える和らげ方【専門家監修】
会議中に突然、顔がカッと熱くなり、汗が噴き出してくる―そんな経験はありませんか? 周囲に気づかれないよう必死でやり過ごしている方も多いのではないでしょうか。 本記事では、東洋医学の視点から更年期に起こるほてりの特徴と、体質に合わせた和らげ方について解説します。自分でできるセルフケアから、専門家に相談するメリットまでご紹介します。 更年期のほてりについての東洋医学的な考え方 ほてりが起こるメカニズム 更年期のほてりは、西洋医学では女性ホルモン(エストロゲン)の減少により、体温を調節する自律神経のバランスが乱れることで起こると考えられています。 一方、東洋医学では「気・血・水」のバランスという観点から捉えます。特に「気」の流れが乱れたり、「陰」の力が弱まったりすることで、体内の熱のバランスが崩れている状態と考えるのが特徴です。 東洋医学では「一人ひとりの体質や生活環境によって、同じほてりでも現れ方や特徴が異なる」という考え方をします。そのため、体質に合わせたアプローチが大切にされています。 体質との関連性 東洋医学では、ほてりの特徴も体質によって違いがあると考えます。以下に代表的な体質傾向の特徴をご紹介します。(あくまで一般的な傾向であり、個人差があります) 熱証傾向の方のほてり 顔が赤くなりやすい 熱感が強く、汗もたくさん出る傾向 口の渇きや喉の乾燥を伴うことも 温かい場所や飲食物で悪化しやすい 陰虚傾向の方のほてり 特に午後から夕方にかけて症状が出やすい ほてりの後に疲れを感じやすい 手のひらや足の裏などにも熱感を感じることも 乾燥感や軽い不眠を伴うことも 気逆傾向の方のほてり 突然上半身に熱が上がってくる感覚 ストレスや緊張で悪化しやすい 胸のつかえ感を伴うことも 落ち着いた環境では比較的おさまりやすい これらの体質傾向は混在することもあり、また生活習慣や季節によっても変化します。体質の傾向を知ることで、より自分に合った対応が見えてくることがあります。 体質別のセルフケアの考え方 ほてりを感じる際、体質の傾向によって日常生活での工夫の仕方も変わってきます。自分の体質傾向に合わせたセルフケアの考え方をご紹介します。 熱証傾向の方のセルフケア 体内の熱が強い傾向にある方は、熱を冷ますアプローチが基本となります。...