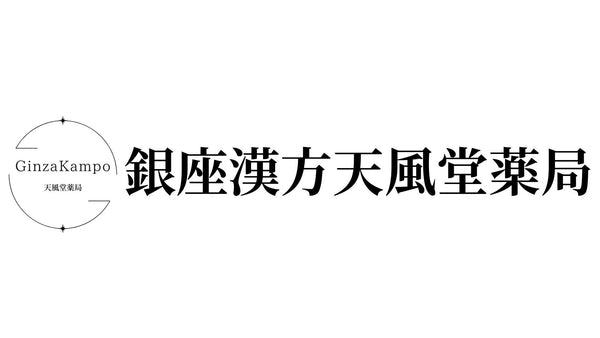会議中に突然、顔がカッと熱くなり、汗が噴き出してくる―そんな経験はありませんか? 周囲に気づかれないよう必死でやり過ごしている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、東洋医学の視点から更年期に起こるほてりの特徴と、体質に合わせた和らげ方について解説します。自分でできるセルフケアから、専門家に相談するメリットまでご紹介します。
更年期のほてりについての東洋医学的な考え方
ほてりが起こるメカニズム
更年期のほてりは、西洋医学では女性ホルモン(エストロゲン)の減少により、体温を調節する自律神経のバランスが乱れることで起こると考えられています。
一方、東洋医学では「気・血・水」のバランスという観点から捉えます。特に「気」の流れが乱れたり、「陰」の力が弱まったりすることで、体内の熱のバランスが崩れている状態と考えるのが特徴です。
東洋医学では「一人ひとりの体質や生活環境によって、同じほてりでも現れ方や特徴が異なる」という考え方をします。そのため、体質に合わせたアプローチが大切にされています。
体質との関連性
東洋医学では、ほてりの特徴も体質によって違いがあると考えます。以下に代表的な体質傾向の特徴をご紹介します。(あくまで一般的な傾向であり、個人差があります)
熱証傾向の方のほてり
- 顔が赤くなりやすい
- 熱感が強く、汗もたくさん出る傾向
- 口の渇きや喉の乾燥を伴うことも
- 温かい場所や飲食物で悪化しやすい
陰虚傾向の方のほてり
- 特に午後から夕方にかけて症状が出やすい
- ほてりの後に疲れを感じやすい
- 手のひらや足の裏などにも熱感を感じることも
- 乾燥感や軽い不眠を伴うことも
気逆傾向の方のほてり
- 突然上半身に熱が上がってくる感覚
- ストレスや緊張で悪化しやすい
- 胸のつかえ感を伴うことも
- 落ち着いた環境では比較的おさまりやすい
これらの体質傾向は混在することもあり、また生活習慣や季節によっても変化します。体質の傾向を知ることで、より自分に合った対応が見えてくることがあります。
体質別のセルフケアの考え方
ほてりを感じる際、体質の傾向によって日常生活での工夫の仕方も変わってきます。自分の体質傾向に合わせたセルフケアの考え方をご紹介します。
熱証傾向の方のセルフケア
体内の熱が強い傾向にある方は、熱を冷ますアプローチが基本となります。
食生活での工夫
- 冷涼性の食材を意識する(きゅうり、すいか、緑茶など)
- 熱を強める食べ物を控える意識(香辛料、アルコール、揚げ物など)
- 適度な水分補給を心がける
生活習慣での工夫
- 涼しい環境作りを意識する(室温調整、衣服の調整など)
- 熱がこもらないよう、適度に汗をかく運動を取り入れる
- 早寝早起きのリズムを整える
東洋医学では、体に溜まった熱を適切に発散させることも大切と考えられています。ただ冷やすだけでなく、適度な運動で余分な熱を発散させるバランスを意識すると良いでしょう。
陰虚傾向の方のセルフケア
体の潤いや栄養が不足している傾向にある方は、滋養を補うアプローチが基本となります。
食生活での工夫
- 滋養のある食材を意識する(黒豆、黒ごま、山芋、きのこ類など)
- 乾燥させる食べ物を控える意識(辛い物、カフェインが多い飲み物など)
- ゆっくり味わって食事をとる時間を大切にする
生活習慣での工夫
- 十分な休息をとり、無理をしないペース配分
- 乾燥対策(室内加湿、こまめな水分補給など)
- リラックスできる時間を意識的に作る
陰虚傾向の方は特に「休息の質」がポイントになります。短時間でも質の良い休息をとることで、体の回復力を高める意識が大切です。
気逆傾向の方のセルフケア
気の流れが上に偏りやすい方は、気の流れを整えるアプローチが基本となります。
食生活での工夫
- 食事は規則正しくバランス良くとる
- 温かい食事を意識する(冷たすぎる飲食物は控える)
- ゆっくり噛んで食べる習慣を大切にする
生活習慣での工夫
- 深呼吸や腹式呼吸を意識的に取り入れる
- 肩や首の緊張をほぐすストレッチ
- 入浴で体をじっくり温め、リラックスする時間をつくる
気逆傾向の方は特に「心の持ち方」がポイントになります。焦りや緊張が症状を悪化させることもあるため、意識的にリラックスする時間を持つことが大切です。
漢方的アプローチの特徴
体質に合わせた考え方
漢方の大きな特徴は「その人の体質や状態に合わせたアプローチ」を大切にすることです。同じ「ほてり」という症状でも、人によって原因や体の状態は異なるため、東洋医学では「証」と呼ばれる体質や状態を見極めることを重視します。
西洋医学のアプローチは症状そのものに直接働きかけることが多い一方、東洋医学では「なぜその症状が現れているのか」という体全体のバランスに注目します。そのため、同じ症状でも人によって異なるアドバイスがなされることがあります。
漢方相談では、問診や舌の状態、脈の状態などから総合的に体質を判断し、一人ひとりに合った対応を考えていきます。
生活習慣との組み合わせの考え方
漢方のもう一つの特徴は、薬だけでなく生活習慣も含めた総合的なアプローチを大切にすることです。東洋医学では「未病」という考え方があり、病気になる前の小さな変化や不調のうちに対応することを重視します。
体質改善のアプローチでは、以下のような視点で総合的に考えていきます:
- 食事の内容や食べ方、飲み物の選択
- 睡眠の質や環境
- 運動や体を動かす習慣
- 心のストレスや休息の取り方
- 季節や環境への対応
漢方は即効性を追求するというよりも、体のバランスを整え、自然治癒力を高めていくことを大切にします。そのため、生活習慣との組み合わせが特に重要と考えられています。
専門家に相談するメリット
銀座天風堂の漢方相談の特徴
天風堂薬局の漢方相談では、東洋医学の考え方に基づいた丁寧な問診と、舌診・脈診などを通じて、一人ひとりの体質や状態を総合的に判断していきます。
当薬局の特徴は以下の点にあります:
- 問診では現在の症状だけでなく、生活背景や過去の体調変化なども丁寧にお聞きします
- 舌の状態や脈の状態から、体の内側の状態を読み取ります
- 体質に合わせた漢方の考え方と、日常生活での養生法をご案内します
- 必要に応じて、西洋医学的なアプローチと組み合わせることも大切にしています
特に更年期の不調は、体質や生活環境、ストレスなど様々な要素が複雑に関わっていることが多いため、総合的な視点でのアドバイスを心がけています。
初回相談の流れ
天風堂薬局での初回漢方相談は、以下のような流れで進みます。
相談前の準備(あれば役立つもの)
- 現在気になる症状やその変化のメモ
- 服用中のお薬があれば、その情報
- 病院で検査を受けたことがある場合は、その結果(可能であれば)
相談当日の流れ
- 問診表へのご記入(約5分)
- 漢方薬剤師による詳しい問診(約20分)
- 現在の症状や不調について
- 生活習慣や食事の傾向について
- 過去の体調変化について など
- 舌診・脈診(約5分)
- 東洋医学的な体質の説明と養生法のアドバイス(約15分)
- 質問やご相談(約10分)
初回相談の所要時間は約50分〜60分です。あなたの状態をしっかり把握するために、十分な時間をかけて対応させていただきます。
まとめと次のステップ
更年期に起こるほてりは、東洋医学では体内の「気・血・水」のバランスの乱れとして捉えます。特に体質によって現れ方や対応が異なることが特徴です。
本記事でご紹介したポイント
- ほてりには「熱証」「陰虚」「気逆」などの体質傾向があり、それぞれ特徴が異なる
- 体質傾向に合わせたセルフケアの基本的な考え方があり、食事や生活習慣での工夫が大切
- 漢方的アプローチでは体質に合わせた総合的な対応を重視する
- 専門家への相談では、詳しい問診と舌診・脈診から個人に合ったアドバイスが受けられる
更年期の不調は一時的なものですが、その期間は人によって異なります。ご自身のペースで、体質に合った対応を見つけていくことが大切です。
今回ご紹介したセルフケアの基本的な考え方を日常生活に取り入れながら、より詳しいアドバイスが必要な場合は、ぜひ専門家にご相談ください。天風堂薬局では、あなたの体質と状態に合わせた東洋医学的なアプローチをご案内しています。
※本記事は東洋医学における考え方をご紹介するものであり、効果効能を保証するものではありません。体調のお悩みがある場合は、医療機関への受診もご検討ください。