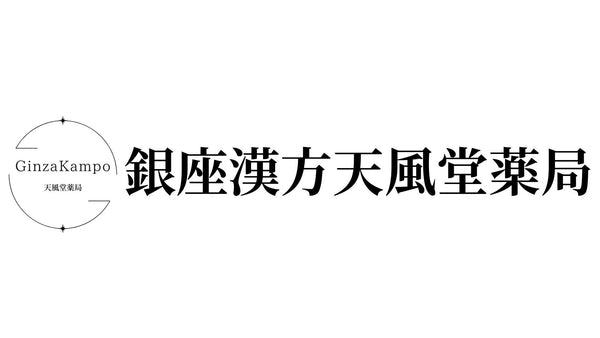突然涙が出てきたり、些細なことでイライラしたり、気分の波を感じることが増えていませんか?更年期を迎えると、身体的な変化だけでなく、心の状態にも変化が現れることがあります。「なぜこんなに感情が不安定になるのだろう」と戸惑っている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、東洋医学の視点から更年期に起こる気分の変化の特徴と、体質に合わせた和らげ方について解説します。自分でできる心のセルフケアから、専門家に相談するメリットまでご紹介します。
更年期の気分変化と東洋医学的な考え方
更年期に心のバランスが変化するメカニズム
更年期の気分変化は、西洋医学では女性ホルモン(エストロゲン)の減少が脳内の神経伝達物質(セロトニンやドーパミンなど)のバランスに影響を与えることで起こると考えられています。
一方、東洋医学では「気・血・水」のバランスという観点から心の状態を捉えます。特に「肝(かん)」と呼ばれる機能が重要とされます。東洋医学における「肝」は、西洋医学の肝臓とは異なり、気の巡りや感情のバランスを調整する働きを担っていると考えられています。
東洋医学では「心身一如」という考え方があり、心と体は互いに密接に影響し合うと考えます。更年期に起こる身体変化が心に影響し、また心の状態が体にも影響するという相互関係の中で、気分の変化を捉えていきます。
体質と気分変化の関連性
東洋医学では、気分の変化の特徴も体質によって違いがあると考えます。以下に代表的な体質傾向の特徴をご紹介します。(あくまで一般的な傾向であり、個人差があります)
肝気鬱結(かんきうっけつ)傾向の方
- イライラしやすく、気分の波が大きい
- 胸や脇腹に詰まった感じがすることも
- ため息が出やすい
- ストレスに敏感で、緊張しやすい
肝陽上亢(かんようじょうこう)傾向の方
- 怒りっぽく、頭に血が上る感じがする
- 頭痛や目の充血を伴うことも
- 顔が熱くなりやすい
- 口が渇きやすい
心脾両虚(しんぴりょうきょ)傾向の方
- 憂うつ感や不安感が強い
- 疲れやすく、気力が出にくい
- 食欲不振や消化不良を伴うことも
- 考え事が多くなり、眠りが浅くなる
これらの体質傾向は混在することもあり、また生活習慣や季節によっても変化します。体質の傾向を知ることで、より自分に合った対応が見えてくることがあります。
体質別の心を整える養生法
気分の変化の特徴や体質によって、日常生活での工夫の仕方も変わってきます。自分の体質傾向に合わせた養生法の考え方をご紹介します。
肝気鬱結(かんきうっけつ)傾向の方の養生法
気の巡りが滞り、イライラしやすい方は、気の流れを促すアプローチが基本となります。
食生活での工夫
- 酸味のある食材を適度に取り入れる(レモン、酢、梅干しなど)
- 新鮮な野菜や果物を積極的に摂る
- アルコールや脂っこい食事は控えめにする
生活習慣での工夫
- 適度な有酸素運動を取り入れる(ウォーキング、ストレッチなど)
- 深呼吸や腹式呼吸を意識的に行う
- 趣味や創作活動など、気分転換できる時間を持つ
- 自然の中で過ごす時間を作る
東洋医学では「疏肝理気(そかんりき)」といって、肝の働きを整え、気の巡りを良くすることを重視します。特に「笑う」ことは気の流れを良くする効果があるとされているので、楽しい時間を意識的に作ることも大切です。
肝陽上亢(かんようじょうこう)傾向の方の養生法
熱が上に昇りやすく、怒りっぽい方は、熱を鎮め、陰を養うアプローチが基本となります。
食生活での工夫
- 清涼感のある食材を意識する(きゅうり、緑茶、菊花茶など)
- 辛い物や刺激物を控える(香辛料、アルコールなど)
- 適度な水分補給を心がける
生活習慣での工夫
- 穏やかな環境での休息を心がける
- 入浴後に頭部を冷やしすぎないようにする
- 静かな音楽を聴く、読書をするなどリラックスできる活動を取り入れる
- 足湯やぬるめの入浴でリラックスする
肝陽上亢傾向の方は特に「心の持ち方」がポイントになります。意識的にゆったりとした気持ちを持つ練習や、小さな幸せを見つける習慣が役立つことがあります。
心脾両虚(しんぴりょうきょ)傾向の方の養生法
気力が低下し、憂うつ感がある方は、気血を補うアプローチが基本となります。
食生活での工夫
- 消化の良い食事を心がける(お粥、スープなどもおすすめ)
- 良質なタンパク質を適量摂る(魚、鶏肉、豆腐など)
- 少量ずつ、ゆっくり食べることを意識する
生活習慣での工夫
- 十分な睡眠と休息を確保する
- 無理をしない範囲で軽い運動を取り入れる
- 好きな香りを楽しむなど、五感を心地よく刺激する
- 信頼できる人との温かい交流を大切にする
心脾両虚傾向の方は特に「休息の質」がポイントになります。ただ横になるだけでなく、心地よいと感じられる環境で積極的に休息を取ることが大切です。
漢方的アプローチの特徴
体質に合わせた考え方
漢方の大きな特徴は「その人の体質や状態に合わせたアプローチ」を大切にすることです。同じ「気分の変化」という症状でも、人によって原因や体の状態は異なるため、東洋医学では「証」と呼ばれる体質や状態を見極めることを重視します。
例えば、肝気鬱結でイライラが強い方と、心脾両虚で気力が低下している方では、アプローチが大きく異なります。漢方相談では、詳しい問診や舌診、脈診などから一人ひとりの体質を判断し、体質に合った対応を考えていきます。
心と体のバランスを整える考え方
漢方的アプローチのもう一つの特徴は、心と体を切り離さず、総合的に捉えることです。東洋医学では、心の状態と体の状態は密接に関わっていると考えます。
心のバランスを整えるアプローチでは、以下のような視点で総合的に考えていきます:
- 食事の内容や食べ方
- 休息と活動のリズム
- 季節や環境の変化への対応
- 感情の表現方法
- 人間関係や社会とのつながり
漢方は即効性よりも、心身のバランスを整え、自己治癒力を高めていくことを大切にします。そのため、生活習慣との組み合わせが特に重要と考えられています。
専門家に相談するメリット
銀座天風堂の漢方相談の特徴
天風堂薬局の漢方相談では、東洋医学の考え方に基づいた丁寧な問診と、舌診・脈診などを通じて、一人ひとりの体質や状態を総合的に判断していきます。
当薬局の特徴は以下の点にあります:
- 現代の生活スタイルに合った実践的なアドバイス
- 西洋医学との連携を大切にした総合的なアプローチ
- 一人ひとりの体質や生活リズムに合わせた細やかな対応
- プライバシーに配慮した安心して相談できる環境
特に更年期の気分変化は、ホルモンバランスの変化だけでなく、生活環境やストレス、人間関係など様々な要素が複雑に関わっていることが多いため、多角的な視点でのアドバイスを心がけています。
初回相談の流れ
天風堂薬局での初回漢方相談は、以下のような流れで進みます。
相談前の準備(あれば役立つもの)
- 気分の変化や体調の変化のメモ(いつ頃から、どのような特徴かなど)
- 服用中のお薬があれば、その情報
- 生活習慣や最近の変化について
相談当日の流れ
- 問診表へのご記入(約5分)
- 漢方薬剤師による詳しい問診(約20分)
- 気分の変化や体調について
- 生活習慣や食事の傾向について
- ストレスや休息について など
- 舌診・脈診(約5分)
- 東洋医学的な体質の説明と養生法のアドバイス(約15分)
- 質問やご相談(約10分)
初回相談の所要時間は約50分〜60分です。あなたの状態をしっかり把握するために、十分な時間をかけて対応させていただきます。
まとめと次のステップ
更年期の気分変化は、東洋医学では「気・血・水」のバランスの乱れ、特に「肝」の機能との関連が深いと考えられています。体質によって気分変化の現れ方や対応が異なることが特徴です。
本記事でご紹介したポイント
- 気分変化には「肝気鬱結」「肝陽上亢」「心脾両虚」などの体質傾向があり、それぞれ特徴が異なる
- 体質傾向に合わせた養生法の基本的な考え方があり、食事や生活習慣での工夫が大切
- 漢方的アプローチでは心と体を総合的に捉え、バランスを整えることを重視する
- 専門家への相談では、詳しい問診と舌診・脈診から個人に合ったアドバイスが受けられる
更年期の気分変化は一時的なものですが、その期間や強さは人によって異なります。ご自身のペースで、体質に合った対応を見つけていくことが大切です。
今回ご紹介した養生法の基本的な考え方を日常生活に取り入れながら、より詳しいアドバイスが必要な場合は、ぜひ専門家にご相談ください。天風堂薬局では、あなたの体質と状態に合わせた東洋医学的なアプローチをご案内しています。
※本記事は東洋医学における考え方をご紹介するものであり、効果効能を保証するものではありません。気分の変化が著しく日常生活に支障がある場合は、医療機関への受診もご検討ください。