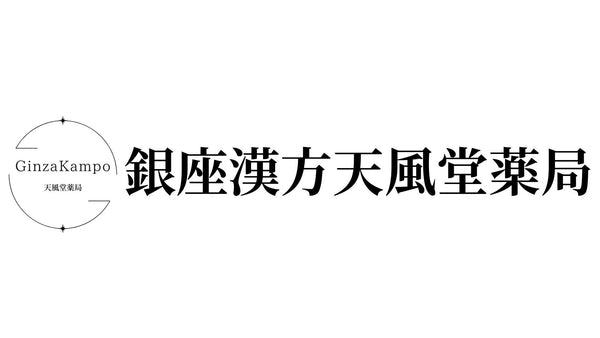「冬だけでなく、夏でも手足が冷える」「温かい部屋でも足先が冷たい」「温めても芯から温まった感じがしない」…更年期に入ってから、こうした冷えの悩みが増えていませんか?ホットフラッシュとは反対に、体の末端の冷えを感じる方も少なくありません。
本記事では、東洋医学の視点から更年期の冷えの特徴と、体質に合わせた漢方的アプローチについて解説します。自分でできる温め方から、専門家に相談するメリットまでご紹介します。
更年期の冷えと東洋医学的な考え方
更年期に冷えが生じるメカニズム
更年期の冷えは、西洋医学では女性ホルモンの減少によって血行が悪くなったり、自律神経のバランスが乱れることで起こると考えられています。特に手足など末端部分の血流が滞りやすくなり、冷えを感じやすくなります。
一方、東洋医学では「気・血・水」のバランスという観点から冷えを捉えます。特に「気」と「血」の巡りが滞ったり、「陽気」と呼ばれる体を温める力が弱まったりすることで、冷えが生じると考えます。
東洋医学では「冷えは万病の元」と言われるほど、体の冷えは様々な不調の原因になると考えられています。冷えのタイプや部位から体の状態を読み取り、根本的なバランスを整えるアプローチを大切にしています。
体質と冷えパターンの関連性
東洋医学では、冷えの特徴も体質によって違いがあると考えます。以下に代表的な体質傾向と冷えの特徴をご紹介します。(あくまで一般的な傾向であり、個人差があります)
気虚(ききょ)傾向の方の冷え
- 全身的に力が入りにくく、体が温まりにくい
- 疲れやすく、動くとしんどい
- 声が小さく、話すのも疲れる
- 汗をかきやすく、風邪をひきやすい
血虚(けっきょ)傾向の方の冷え
- 手足の先が特に冷えやすい
- 顔色が青白く、唇や爪の色が薄い
- 肌が乾燥しやすい
- めまいや動悸を感じることも
陽虚(ようきょ)傾向の方の冷え
- お腹や背中、腰など体の芯が冷える感じ
- 温かいものを好み、寒さに弱い
- 水分をとると余計に冷える感じがする
- 朝起きるのがつらい
瘀血(おけつ)傾向の方の冷え
- 局所的に冷えや痛みを感じる
- 皮膚に内出血ができやすい
- 肌の血色が悪く、シミができやすい
- 生理痛が強かった、または不順だった
これらの体質傾向は混在することもあり、また生活習慣や季節によっても変化します。体質の傾向を知ることで、より自分に合った対応が見えてくることがあります。
体質別の冷えを改善する養生法
冷えの特徴や体質によって、日常生活での工夫の仕方も変わってきます。自分の体質傾向に合わせた養生法の考え方をご紹介します。
気虚(ききょ)傾向の方の養生法
体を動かす力が弱く全身が温まりにくい方は、気を補うアプローチが基本となります。
食生活での工夫
- 消化の良い温かい食事を心がける
- 適度な甘味のある食材を意識する(さつまいも、かぼちゃなど)
- 少量ずつ、ゆっくり食べることを意識する
生活習慣での工夫
- 無理をせず、適度な休息をとる
- 少しずつ体を動かす習慣をつける
- 深呼吸や軽いストレッチを取り入れる
- 首や肩を温める工夫をする
気虚傾向の方は特に「過労」に注意が必要です。自分のペースを大切にし、無理をしない範囲で体を動かすことが冷え改善のポイントになります。
血虚(けっきょ)傾向の方の養生法
手足の先が冷えやすく血色が悪い方は、血を補うアプローチが基本となります。
食生活での工夫
- 血を作る食材を意識する(レバー、ほうれん草、黒豆など)
- 良質なタンパク質を適量摂る
- 鉄分を含む食材を積極的に取り入れる
生活習慣での工夫
- 十分な睡眠を心がける
- 入浴でじっくり体を温める
- 手足の指先のマッサージをこまめに行う
- 冷えやすい部分を重点的に保温する
血虚傾向の方は特に「血行促進」がポイントになります。末端まで血液を届けるために、手足を温めるだけでなく、血の巡りを良くする工夫が大切です。
陽虚(ようきょ)傾向の方の養生法
体の芯から冷える方は、陽気を補うアプローチが基本となります。
食生活での工夫
- 温性の食材を意識する(生姜、ねぎ、にんにくなど)
- 温かい飲み物を適度に摂る
- 冷たい飲食物を避ける
- 腹部を温めながら食事をとる
生活習慣での工夫
- お腹や腰、背中を重点的に温める
- 湯たんぽやカイロで就寝時も保温する
- 入浴はぬるめのお湯にゆっくりつかる
- 冷えやすい場所への外出時は厚着を心がける
陽虚傾向の方は特に「体の芯を温める」ことがポイントになります。表面だけでなく、内側から温まる感覚を大切にした養生が効果的です。
瘀血(おけつ)傾向の方の養生法
局所的に冷えや痛みがある方は、血の流れを改善するアプローチが基本となります。
食生活での工夫
- 血流を促進する食材を意識する(黒酢、玉ねぎ、にんにくなど)
- 適度な酸味のある食材を取り入れる
- 油っこいものや刺激物は控えめにする
生活習慣での工夫
- 適度な有酸素運動を続ける
- 冷えている部分を重点的にマッサージする
- 入浴時に冷えている部分を丁寧にさする
- 半身浴や足湯で下半身を温める
瘀血傾向の方は特に「血流の停滞を改善する」ことがポイントになります。同じ姿勢を長時間続けないように意識し、こまめに体を動かすことが大切です。
漢方的アプローチの特徴
体質に合わせた考え方
漢方の大きな特徴は「その人の体質や状態に合わせたアプローチ」を大切にすることです。同じ「冷え」という症状でも、人によって原因や体の状態は異なるため、東洋医学では「証」と呼ばれる体質や状態を見極めることを重視します。
例えば、気虚で全身的に力が入りにくい方と、瘀血で局所的に冷えがある方では、アプローチが大きく異なります。漢方相談では、詳しい問診や舌診、脈診などから一人ひとりの体質を判断し、体質に合った対応を考えていきます。
体の巡りを整える考え方
漢方のもう一つの特徴は「巡り」を重視することです。気血の巡りが滞ると冷えや様々な不調が生じると考え、巡りを良くすることを大切にします。
冷えを改善するアプローチでは、以下のような視点で総合的に考えていきます:
- 食べ物の温熱性(体を温めるか冷やすか)
- 体を動かすリズムや質
- 保温と発散のバランス
- 精神的な緊張や休息
- 季節や環境変化への対応
漢方は即効性よりも、体のバランスを整え、自然治癒力を高めていくことを大切にします。そのため、生活習慣との組み合わせが特に重要と考えられています。
専門家に相談するメリット
銀座天風堂の漢方相談の特徴
天風堂薬局の漢方相談では、東洋医学の考え方に基づいた丁寧な問診と、舌診・脈診などを通じて、一人ひとりの体質や状態を総合的に判断していきます。
当薬局の特徴は以下の点にあります:
- 現代の生活スタイルに合った実践的なアドバイス
- 西洋医学との連携を大切にした総合的なアプローチ
- 一人ひとりの体質や生活リズムに合わせた細やかな対応
- 季節や環境変化に合わせた継続的なフォロー
特に更年期の冷えは、ホルモンバランスの変化だけでなく、長年の生活習慣や体質の影響も大きいため、多角的な視点でのアドバイスを心がけています。
初回相談の流れ
天風堂薬局での初回漢方相談は、以下のような流れで進みます。
相談前の準備(あれば役立つもの)
- 冷えの部位や時間帯、特徴のメモ(いつ頃から、どのような特徴かなど)
- 体を温めるために試してきた方法とその効果
- 服用中のお薬があれば、その情報
相談当日の流れ
- 問診表へのご記入(約5分)
- 漢方薬剤師による詳しい問診(約20分)
- 冷えの状態や特徴について
- 生活習慣や食事の傾向について
- その他の体調や過去の健康状態について など
- 舌診・脈診(約5分)
- 東洋医学的な体質の説明と養生法のアドバイス(約15分)
- 質問やご相談(約10分)
初回相談の所要時間は約50分〜60分です。あなたの体質や状態をしっかり把握するために、十分な時間をかけて対応させていただきます。
まとめと次のステップ
更年期の冷えは、東洋医学では「気・血・水」のバランスの乱れ、特に「気血の巡り」や「陽気の不足」との関連が深いと考えられています。体質によって冷えの現れ方や対応が異なることが特徴です。
本記事でご紹介したポイント
- 冷えには「気虚」「血虚」「陽虚」「瘀血」などの体質傾向があり、それぞれ特徴が異なる
- 体質傾向に合わせた養生法の基本的な考え方があり、食事や生活習慣での工夫が大切
- 漢方的アプローチでは「巡り」を重視し、バランスを整えることを大切にする
- 専門家への相談では、詳しい問診と舌診・脈診から個人に合ったアドバイスが受けられる
更年期の冷えは体質改善と適切な養生法で和らげることができます。ご自身のペースで、体質に合った対応を見つけていくことが大切です。
今回ご紹介した養生法の基本的な考え方を日常生活に取り入れながら、より詳しいアドバイスが必要な場合は、ぜひ専門家にご相談ください。天風堂薬局では、あなたの体質と状態に合わせた東洋医学的なアプローチをご案内しています。
※本記事は東洋医学における考え方をご紹介するものであり、効果効能を保証するものではありません。冷えに関する深刻な症状がある場合は、医療機関への受診もご検討ください。