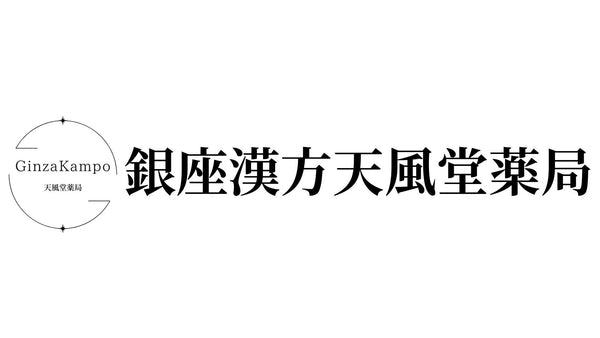「なかなか妊娠しない…」そんな不安や焦りを感じているあなたは、決して一人ではありません。日本では約5.5組に1組のカップルが不妊の問題に直面しています。不妊とは単なる「妊娠できない」状態ではなく、「妊娠までに時間がかかっている状態」です。
原因は女性側だけでなく男性側にもあり、また両方または原因不明のケースもあります。本記事では、不妊の基礎知識から検査・治療法、心のケア、生活改善まで幅広く解説します。正しい知識と適切なサポートがあれば、多くのカップルが前向きに不妊と向き合い、自分たちらしい家族づくりへの道を見つけることができるのです。不妊治療の進歩や社会的支援の拡充も進む今、希望を持って一歩を踏み出すための情報をお届けします。
不妊検査を受けるタイミング
「不妊かも」と思ったらいつ病院へ行くべきか
一般的には、避妊せずに規則的な性生活を送っているにもかかわらず、1年経っても妊娠しない場合に不妊検査を検討するタイミングといわれています。しかし、女性の年齢や既往歴によってはもっと早い段階での受診が推奨されます。特に女性が35歳以上の場合は6ヶ月、40歳以上では3ヶ月を目安に受診を検討するのが良いでしょう。
また、月経不順や生理痛がひどい、子宮内膜症や子宮筋腫などの診断を受けたことがある、過去に性感染症にかかったことがある、男性側に泌尿器科的な問題がある場合なども、早めの受診が勧められます。「まだ大丈夫」と様子を見ることで貴重な時間を失うこともあるため、少しでも気になる場合は専門医に相談することをおすすめします。
年齢別の受診タイミングの目安
年齢によって不妊検査を受けるタイミングは異なります。35歳未満の女性の場合、避妊せずに12ヶ月経過しても妊娠しない場合が検査開始の目安です。35~37歳では6ヶ月、38~39歳では3~6ヶ月、40歳以上では3ヶ月が一般的な目安とされています。これは、加齢に伴う妊孕性(にんようせい:妊娠する力)の低下を考慮したものです。
女性の年齢が上がるにつれて卵子の質・量の低下や染色体異常のリスクが高まるため、早期に原因を特定し、適切な治療を開始することが重要となります。男性側の年齢も重要な要素ですが、女性ほど明確な年齢基準はなく、一般的には女性の年齢を優先して受診タイミングを判断することが多いです。
ただし、男性側に精巣の疾患や性機能障害など明らかな問題がある場合は、年齢に関わらず早期の受診が推奨されます。
産婦人科と不妊専門クリニックの選び方
不妊検査・治療は産婦人科でも不妊専門クリニックでも受けることができますが、施設によって対応できる検査や治療の範囲は異なります。一般的に、タイミング法や人工授精などの基本的な治療は多くの産婦人科で受けられますが、体外受精や顕微授精などの高度生殖医療を希望する場合は、それらに対応した不妊専門クリニックを選ぶ必要があります。
クリニック選びのポイントとしては、①通院のしやすさ(立地や診療時間)、②医師の専門性と経験、③施設の設備や技術レベル(成功率など)、④費用、⑤医師やスタッフの対応の丁寧さ、などが挙げられます。
また、実際に両方受診してみて相性の良い方を選ぶという方法もあります。不妊治療は長期に渡ることも多いため、信頼できる医師との出会いは重要です。クリニック選びで悩む場合は、友人や先輩ママの体験談、インターネットの口コミなども参考にしつつ、最終的には実際に足を運んで自分の目で確かめることをおすすめします。
女性が受ける不妊検査
基礎体温とホルモン検査
女性の不妊検査の基本となるのが基礎体温測定とホルモン検査です。基礎体温は毎朝起きたときに、体を動かす前に測定する体温で、排卵の有無や黄体機能を知る手がかりとなります。一般的に排卵前は低温期(36.2~36.5℃)、排卵後は高温期(36.5~36.8℃)と二相性のパターンを示します。3~6ヶ月分の基礎体温表があると診断の参考になります。
ホルモン検査では、主に卵胞刺激ホルモン(FSH)、黄体形成ホルモン(LH)、エストラジオール(E2)、プロゲステロン、プロラクチン、テストステロン、甲状腺ホルモン(TSH、FT3、FT4)などを測定します。
特に、月経3日目前後のFSH値は卵巣予備能(残りの卵子の量)を反映し、10mIU/mL以上だと低下傾向にあるとされます。また、抗ミュラー管ホルモン(AMH)は年齢に関係なく卵巣予備能を評価できる重要な指標として近年注目されています。これらの検査により、排卵障害の有無やその背景にある内分泌異常を診断することができます。
超音波検査と卵巣機能検査
経腟超音波検査は不妊診療において最も基本的かつ重要な検査の一つです。この検査では、子宮の大きさや形状、内膜の厚さ、卵巣の大きさ、卵胞(卵子の入った袋)の数や発育状態、子宮筋腫や卵巣嚢腫などの異常の有無を確認することができます。
特に排卵前後には、優位卵胞(その周期で排卵する予定の最も大きな卵胞)の成長を観察したり、排卵の有無を確認したりするために複数回の検査が行われることもあります。
卵巣機能検査としては、前述のAMH測定や月経3日目のFSH値に加え、アンテラルフォリクルカウント(AFC:超音波で観察できる2~9mmの小さな卵胞の数)も重要です。AFCが両側で10個以上あれば卵巣予備能は良好とされ、5個未満だと低下している可能性があります。
これらの検査結果を総合的に判断することで、女性の卵巣年齢(生物学的な卵巣の状態)を推測し、治療方針や排卵誘発法の選択に役立てます。超音波検査は痛みがほとんどなく、被ばくもないため、不妊治療中は頻繁に行われる基本的な検査です。
子宮内膜検査
子宮内膜は受精卵が着床する場所であり、その状態や受容性は妊娠成立に重要な役割を果たします。子宮内膜検査では、内膜の厚さや性状、血流などを評価します。一般的に着床に適した内膜の厚さは8~12mm程度といわれていますが、個人差もあります。
また、子宮内膜日付診(子宮内膜の成熟度と月経周期の一致を確認する検査)や子宮内膜炎の有無を調べる検査なども行われることがあります。
近年では、着床の窓(着床に最適な時期)を特定するERA(Endometrial Receptivity Analysis)検査や、子宮内細菌叢(マイクロバイオーム)を評価する検査なども開発されていますが、これらはまだ研究段階の検査法です。
子宮内膜検査は主に子宮内膜の一部を採取して行われるため、軽度の痛みや出血を伴うことがありますが、短時間で終了します。特に反復着床不全(体外受精を繰り返しても妊娠に至らない状態)の方には、子宮内膜の詳細な検査が推奨されることがあります。
男性が受ける不妊検査
精液検査の内容と見方
男性不妊の基本検査となるのが精液検査です。この検査では、精液の量、精子濃度(1mlあたりの精子数)、精子の運動率や正常形態率などを調べます。
WHO(世界保健機関)の基準によると、正常値は精液量1.5ml以上、精子濃度1,500万/ml以上、総精子数3,900万以上、前進運動精子32%以上、正常形態精子4%以上とされています。検査のためには2~7日間の禁欲期間が必要で、主に用手法(マスターベーション)で採取した精液を分析します。
多くの医療機関では、精液の提出場所や方法について配慮がなされていますが、自宅で採取し持参することも可能な場合があります。結果の解釈は医師によって行われますが、一度の検査結果だけでは判断せず、2~3ヶ月間隔で2回以上の検査を行うことが推奨されています。
これは精子の状態が様々な要因(体調、環境、ストレスなど)によって変動するためです。精液検査の結果によって、自然妊娠の可能性や最適な治療法(タイミング法、人工授精、体外受精など)が判断されます。
ホルモン検査
男性の生殖機能に関わるホルモンバランスを評価するため、血液検査が行われます。主な検査項目は、FSH(卵胞刺激ホルモン)、LH(黄体形成ホルモン)、テストステロン、プロラクチン、甲状腺ホルモンなどです。
FSHは精子形成の状態を反映し、高値の場合は精巣の機能低下が疑われます。LHとテストステロンのバランスも重要で、テストステロン低値・LH高値は原発性性腺機能低下(精巣自体の問題)、テストステロン低値・LH低値は続発性性腺機能低下(脳下垂体の問題)を示唆します。
また、プロラクチンの異常高値は性欲低下や勃起障害の原因となることがあります。これらのホルモン検査は特に無精子症や高度乏精子症の場合に重要で、原因の特定や治療方針の決定に役立ちます。
ホルモン異常が判明した場合、内分泌治療(ホルモン補充療法など)が行われることもあります。採血のみの簡便な検査ですが、ホルモン値には日内変動があるため、通常は午前中に行われることが多いです。
精巣超音波検査とその他の検査
精液検査やホルモン検査で異常が見つかった場合や、触診で精巣の異常が疑われる場合には、精巣の超音波検査が行われることがあります。この検査では、精巣の大きさや内部構造、精索静脈瘤(せいさくじょうみゃくりゅう:静脈の拡張による血液のうっ滞)の有無などを評価します。
特に、無精子症の患者さんでは、精巣生検(精巣の一部を採取して顕微鏡で観察する検査)を行う前に超音波検査で精巣の状態を確認することが重要です。
また、射精障害が疑われる場合には、射精後尿検査(逆行性射精の有無を確認)や神経学的検査が追加されることもあります。精索静脈瘤が見つかった場合は、その程度によって手術適応が判断されます。
その他、必要に応じて染色体検査やY染色体微小欠失検査などの遺伝学的検査が行われることもあります。精巣超音波検査は痛みを伴わない非侵襲的な検査ですが、精巣生検は局所麻酔下で行われるため、ある程度の痛みや術後の不快感を伴うことがあります。
よくある質問(Q&A)
Q1: 不妊治療はいつから始めるべきですか?
A1: 一般的には、35歳未満の女性であれば避妊せずに12ヶ月経っても妊娠しない場合、35歳以上であれば6ヶ月経っても妊娠しない場合に不妊検査を検討するタイミングとされています。
ただし、月経不順や子宮内膜症などの既往歴がある場合は、もっと早い段階での受診が推奨されます。男性側にも泌尿器科的な問題がある場合は早めの受診が望ましいでしょう。不妊治療は時間との戦いでもあるため、特に女性が35歳を超える場合は、気になるようであれば早めに専門医に相談することをお勧めします。
Q2: 不妊治療の成功率はどれくらいですか?
A2: 不妊治療の成功率は治療法や年齢、不妊原因によって大きく異なります。一般的には、タイミング法では1周期あたり約10~15%、人工授精では約5~15%、体外受精では35歳未満で約40~50%、35~37歳で約35~40%、38~40歳で約25~30%、41~42歳で約15~20%、43歳以上では10%未満とされています。
これらは1回の治療周期あたりの臨床妊娠率であり、累積妊娠率(複数回の治療を合わせた妊娠率)はこれより高くなります。ただし、妊娠しても流産するリスクもあり、これも年齢とともに上昇します。成功率は医療機関によっても差があるため、複数の施設の実績を比較することも参考になります。
Q3: 不妊治療中の仕事との両立はどうすればよいですか?
A3: 不妊治療は通院頻度が高く、特に体外受精では急な診察が必要になることも多いため、仕事との両立は大きな課題です。
効果的な両立のためには、①可能であれば職場に状況を伝え理解を求める(プライバシーに配慮した相談体制があるか確認する)、②不妊治療に理解のある職場環境や柔軟な勤務体制を持つ企業を選ぶ、③時差出勤やフレックスタイム、在宅勤務などの制度を活用する、④通院のために有給休暇や時間単位の休暇を効率的に使う、⑤通院しやすい立地のクリニックを選ぶ、⑥同じような状況の方との情報交換で両立のコツを学ぶ、などの工夫が効果的です
。2022年4月からは不妊治療のための休暇制度の整備や相談体制の構築が事業主の努力義務となりましたので、職場の制度を確認することをお勧めします。治療と仕事の優先順位は個人の価値観や状況によって異なりますので、パートナーとよく話し合い、無理のない計画を立てることが大切です。