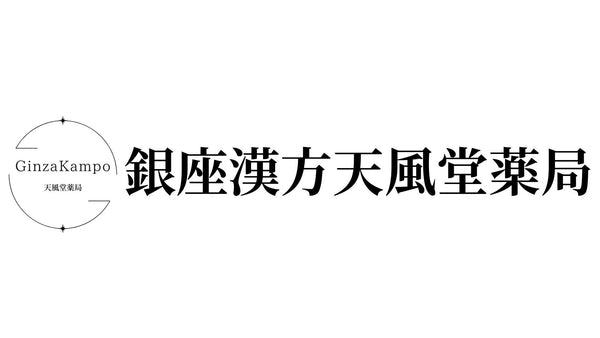「なかなか妊娠しない…」そんな不安や焦りを感じているあなたは、決して一人ではありません。日本では約5.5組に1組のカップルが不妊の問題に直面しています。不妊とは単なる「妊娠できない」状態ではなく、「妊娠までに時間がかかっている状態」です。
原因は女性側だけでなく男性側にもあり、また両方または原因不明のケースもあります。本記事では、不妊の基礎知識から検査・治療法、心のケア、生活改善まで幅広く解説します。正しい知識と適切なサポートがあれば、多くのカップルが前向きに不妊と向き合い、自分たちらしい家族づくりへの道を見つけることができるのです。不妊治療の進歩や社会的支援の拡充も進む今、希望を持って一歩を踏み出すための情報をお届けします。
女性側の原因
排卵障害とホルモンバランスの乱れ
女性の不妊原因の約25~30%を占めるのが排卵障害です。これは視床下部-下垂体-卵巣の軸に関わるホルモンバランスの乱れによって引き起こされます。多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)はその代表例で、若い女性の5~10%が罹患しているとされています。
他にも甲状腺機能異常、高プロラクチン血症、早発閉経、ストレスや過度なダイエット、激しい運動による体重減少も排卵障害の原因となります。基礎体温表を付けることで排卵の有無を確認することが可能で、ホルモン検査と合わせて診断されます。治療はホルモン剤による排卵誘発が主となりますが、原因に応じた適切な治療法が選択されます。
卵管の異常と通過障害
卵管は精子と卵子の出会いの場所であり、受精卵を子宮まで運ぶパイプラインの役割を果たします。卵管の閉塞や癒着があると、精子と卵子の出会いが妨げられ、不妊の原因となります。卵管障害は女性不妊の約20~30%を占め、その主な原因としては骨盤内感染症(PID)、子宮内膜症、骨盤手術後の癒着、先天的な異常などがあります。
特にクラミジアなどの性感染症は無症状のまま卵管を損傷させることがあり、若い女性の不妊原因として増加傾向にあります。卵管造影検査によって卵管の状態を確認することができ、閉塞の程度や位置によって卵管鏡下手術や体外受精などの治療方法が選択されます。
子宮内膜症や子宮筋腫の影響
子宮内膜症は子宮内膜様の組織が子宮外に生着し、炎症や癒着を引き起こす疾患で、生殖年齢女性の約10%に見られます。不妊女性では30~50%と高率に認められることから、不妊との関連が強いと考えられています。子宮内膜症は骨盤内の炎症により卵管機能の低下や卵巣予備能の低下、受精卵の着床障害などを引き起こします。
また、子宮筋腫は生殖年齢女性の20~40%に見られる良性腫瘍で、大きさや位置によっては不妊の原因となります。特に粘膜下筋腫は子宮内腔を変形させて着床障害や流産の原因となることがあります。
治療法としては、腹腔鏡手術や薬物療法、筋腫の場合は筋腫核出術などが行われますが、症状や妊娠希望の有無によって個別に判断されます。
加齢による卵子の質と量の低下
女性は胎児期に約700万個の卵子を持って生まれますが、出生時には約200万個、思春期には約30~40万個まで減少し、その後も月経周期ごとに減少し続けます。
さらに、加齢に伴い残存する卵子の質も低下するため、35歳を過ぎると不妊リスクは徐々に高まり、40歳以降は急激に上昇します。卵子の質の低下は主に染色体異常の増加として現れ、これが高齢妊娠での流産率上昇や先天的異常リスクの増加の背景となっています。
年齢による卵子への影響は個人差もありますが、抗ミュラー管ホルモン(AMH)検査や卵胞刺激ホルモン(FSH)値などで卵巣予備能を評価することができます。加齢による影響は避けられませんが、若いうちからの健康管理と計画的なライフプランニングが重要です。
男性側の原因
精子の数・運動率・形態異常
男性不妊の主な原因は精子の異常であり、精液検査で評価されます。WHOの基準によると、正常な精液は1mlあたり1,500万個以上の精子を含み、そのうち32%以上が前進運動性を持ち、正常形態の精子が4%以上含まれる必要があります。
これらの値が基準を下回ると、「乏精子症」(精子数の減少)、「精子無力症」(運動率の低下)、「奇形精子症」(形態異常の増加)などと診断されます。
これらの異常は一時的なものから永続的なものまで様々で、発熱や薬物、環境要因、生活習慣、遺伝的要因など多くの原因によって引き起こされます。治療法は原因によって異なりますが、生活習慣の改善、薬物療法、手術療法、または人工授精や顕微授精などの生殖補助医療が選択されます。
精路通過障害
精路通過障害は、精巣で生成された精子が射精されるまでの経路(精巣上体、精管、射精管など)のどこかに閉塞や障害がある状態です。男性不妊の約5~10%を占めると言われています。
先天的な原因としては精管形成不全や精管欠損などがあり、後天的な原因としては精巣上体炎や前立腺炎などの感染症、鼠径ヘルニアや精索静脈瘤の手術後の癒着、精管結紮術(避妊手術)などがあります。
精路通過障害の場合、精巣では正常に精子が作られているにもかかわらず、精液中に精子が見られない「閉塞性無精子症」となります。診断は精液検査に加え、精管触診、超音波検査、精巣生検などで行われます。
治療法としては、閉塞部位によって精管吻合術や精巣上体精管吻合術などの外科的治療、または精巣内精子回収法(TESE)と顕微授精(ICSI)の組み合わせが選択されます。
勃起・射精障害
性機能障害も男性不妊の一因となります。勃起障害(ED)は性行為に十分な勃起を得られない、または維持できない状態で、心理的要因や血管系・神経系の問題、薬剤の副作用など様々な原因で生じます。
また、射精障害には逆行性射精(精液が膀胱内に逆流する)、射精遅延、無射精などがあり、自律神経障害、薬剤の影響、手術後の合併症などが原因となります。
これらの障害がある場合、タイミング法での妊娠が難しくなるため、状況に応じて薬物療法、心理療法、または人工授精や体外受精などの生殖補助医療が用いられます。特に糖尿病患者や前立腺手術後の患者では射精障害のリスクが高まるため、医師との早めの相談が重要です。
加齢による精子の質の変化
女性ほど明確な年齢制限はないものの、男性も加齢とともに生殖能力は低下します。研究によれば、35歳を超えると精子の量、運動率、正常形態率が徐々に低下することが分かっています。
特に45歳以降では遺伝子断片化や染色体異常を持つ精子の割合が増加し、これにより妊娠までの期間延長、流産率の上昇、子どもの先天的疾患リスクの増加などが報告されています。
また、精巣の血管変化や抗酸化能力の低下、テストステロン値の減少なども加齢に伴う変化として知られています。
ただし、加齢の影響は生活習慣や健康状態によって個人差が大きく、適切な健康管理によってある程度は質の維持が可能です。喫煙や過度の飲酒を避け、バランスの良い食事と適度な運動を心がけることが推奨されます。
原因不明の不妊(機能性不妊)
原因不明不妊の割合と特徴
一般的な不妊検査をすべて行っても、約20~30%のカップルでは明確な不妊原因が見つからない「原因不明不妊」の状態となります。これは「機能性不妊」とも呼ばれ、基本的な生殖機能には異常が見られないにもかかわらず、妊娠に至らない状態を指します。
原因不明不妊のカップルの特徴として、①検査では発見できない微細な異常が複合的に存在している可能性、②年齢が高めであることが多い、③自然妊娠率は決してゼロではない(年間約15~20%が自然妊娠する)、などが挙げられます。原因不明だからといって諦める必要はなく、タイミング法から始めて段階的に治療法を検討していくアプローチが一般的です。
検査では分からない微細な問題
現在の標準的な不妊検査では捉えきれない微細な問題として、①卵子の質的異常(染色体異常や機能低下)、②精子と卵子の受精能力の問題、③受精後の胚発育障害、④着床に関わる分子レベルの異常、⑤免疫学的な問題などが考えられます。
例えば、基礎的な精液検査では「正常」と判定された精子でも、精子DNAの断片化率が高いと受精率や胚発育率が低下することが知られています。また、排卵はしているものの排出される卵子の質が低い場合もあります。
こうした微細な問題は標準検査では見つからないため、治療を通じて間接的に評価することになります。例えば、体外受精で受精しにくい、胚発育が悪いといった所見から推測されることがあります。
免疫的要因と着床障害
免疫系の異常も原因不明不妊の背景にある可能性があります。特に、抗精子抗体や抗リン脂質抗体などの自己抗体は、精子の動きを妨げたり、受精卵の着床を阻害したりすることがあります。
また、子宮内膜の免疫環境の異常も着床障害の原因となることが分かってきています。正常な着床のためには、子宮内膜の受容性(着床の準備状態)が整っていることが重要ですが、この受容性は様々な因子によって調節されており、そのバランスが崩れると着床障害につながります。
近年では子宮内膜の受容性を評価する新たな検査法(ERA検査など)も開発されていますが、まだ研究段階のものも多く、すべての医療機関で受けられるわけではありません。こうした免疫的・着床に関わる問題が疑われる場合は、不妊専門医との相談が重要です。適切な治療法としては、低用量アスピリン療法、ステロイド療法、免疫グロブリン療法などが考慮されることがあります。
よくある質問(Q&A)
Q1: 不妊治療はいつから始めるべきですか?
A1: 一般的には、35歳未満の女性であれば避妊せずに12ヶ月経っても妊娠しない場合、35歳以上であれば6ヶ月経っても妊娠しない場合に不妊検査を検討するタイミングとされています。
ただし、月経不順や子宮内膜症などの既往歴がある場合は、もっと早い段階での受診が推奨されます。男性側にも泌尿器科的な問題がある場合は早めの受診が望ましいでしょう。不妊治療は時間との戦いでもあるため、特に女性が35歳を超える場合は、気になるようであれば早めに専門医に相談することをお勧めします。
Q2: 不妊治療の成功率はどれくらいですか?
A2: 不妊治療の成功率は治療法や年齢、不妊原因によって大きく異なります。一般的には、タイミング法では1周期あたり約10~15%、人工授精では約5~15%、体外受精では35歳未満で約40~50%、35~37歳で約35~40%、38~40歳で約25~30%、41~42歳で約15~20%、43歳以上では10%未満とされています。
これらは1回の治療周期あたりの臨床妊娠率であり、累積妊娠率(複数回の治療を合わせた妊娠率)はこれより高くなります。ただし、妊娠しても流産するリスクもあり、これも年齢とともに上昇します。成功率は医療機関によっても差があるため、複数の施設の実績を比較することも参考になります。
Q3: 不妊治療中の仕事との両立はどうすればよいですか?
A3: 不妊治療は通院頻度が高く、特に体外受精では急な診察が必要になることも多いため、仕事との両立は大きな課題です。
効果的な両立のためには、①可能であれば職場に状況を伝え理解を求める(プライバシーに配慮した相談体制があるか確認する)、②不妊治療に理解のある職場環境や柔軟な勤務体制を持つ企業を選ぶ、③時差出勤やフレックスタイム、在宅勤務などの制度を活用する、④通院のために有給休暇や時間単位の休暇を効率的に使う、⑤通院しやすい立地のクリニックを選ぶ、⑥同じような状況の方との情報交換で両立のコツを学ぶ、などの工夫が効果的です。
2022年4月からは不妊治療のための休暇制度の整備や相談体制の構築が事業主の努力義務となりましたので、職場の制度を確認することをお勧めします。治療と仕事の優先順位は個人の価値観や状況によって異なりますので、パートナーとよく話し合い、無理のない計画を立てることが大切です。