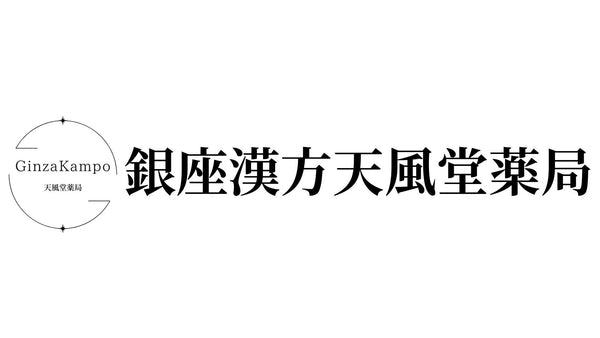監修:銀座漢方天風堂薬局 薬剤師 柳澤謙行(漢方薬剤師歴45年・日本東洋医学会会員)
"なぜ友人と同じダイエット法をしても、私だけ効果が出ないのだろう…"
"どんな方法を試しても長続きしない…"
このような悩みを抱えていませんか?
東洋医学では、一人ひとり異なる「体質」に着目します。同じ食事法でも、人によって合う・合わないがあるのは当然なのです。
この記事では、東洋医学の視点から、自分の体質に合った食生活の選び方について解説します。自分の体質を知り、それに合った食習慣を取り入れることで、無理なく心地よい生活リズムを整えるヒントを見つけていただければ幸いです。
目次
人それぞれ違う「体質」とは?東洋医学の考え方
東洋医学における体質の基本概念
東洋医学では、一人ひとりの体質は先天的要素(生まれ持った特徴)と後天的要素(生活習慣や環境の影響)によって形成されると考えます。
西洋医学がカロリー計算や栄養素といった普遍的・数値的な視点で食事を捉えるのに対し、東洋医学では「その人にとって何が適しているか」という個別的な視点を重視します。これは異なるアプローチであり、どちらが正しいというものではなく、両方の視点を持つことで、より自分に合った方法を見つけやすくなります。
自分の体質を知ることのメリット
体質を知ることで、なぜ特定の食べ物や環境で調子が良くなったり悪くなったりするのかが理解できるようになります。「みんなが良いと言っているから」ではなく、「自分の体質に合っているから」という理由で食事や生活習慣を選べるようになれば、無理なく続けられる可能性が高まります。
自己理解が深まることで、「こうあるべき」という固定観念から解放され、自分に合った心地よい選択ができるようになるのです。
漢方で考える基本的な体質タイプとその特徴
東洋医学では体質をいくつかのタイプに分類します。ここでは、食習慣と特に関連の深い代表的なタイプをご紹介します。
気虚(ききょ)タイプの特徴と傾向
気虚は「気」(生命エネルギー)が不足している状態です。
特徴的な傾向:
- 疲れやすく、元気がでない
- 声が小さく、息切れしやすい
- 汗をかきやすい
- 食欲はあるが消化力が弱い傾向
- 午後になると特に疲れを感じることが多い
食習慣の傾向:
- 消化に時間がかかる食べ物が負担になりやすい
- 冷たいものの摂り過ぎで調子を崩しやすい
- 少量でもこまめに食べた方が調子が良い傾向
気滞(きたい)タイプの特徴と傾向
気滞は「気」の流れが滞っている状態です。
特徴的な傾向:
- ストレスを感じやすい
- 胸やみぞおちが張った感じがする
- 気分の浮き沈みがある
- イライラしやすい
- 満腹感を得にくく食べ過ぎる傾向
食習慣の傾向:
- ストレスで食欲が増減しやすい
- 早食いの傾向がある
- 緊張すると消化不良になりやすい
水滞(すいたい)タイプの特徴と傾向
水滞は水分代謝がスムーズでなく、体内に水分がとどまりやすい状態です。
特徴的な傾向:
- むくみやすい
- 朝と夜で体重の変動が大きい
- 湿度の高い季節に調子が悪くなる
- 重だるさを感じやすい
- 水分の摂り過ぎで調子を崩しやすい
食習慣の傾向:
- 冷たい飲み物が苦手な傾向
- 水分を多く含む食品で膨満感を感じやすい
- 塩分の取り過ぎで調子を崩しやすい
血虚(けっきょ)タイプの特徴と傾向
血虚は「血」(栄養を運ぶ血液とその働き)が不足している状態です。
特徴的な傾向:
- 顔色が冴えない
- 爪や唇の色が薄い
- めまいや立ちくらみがある
- 肌が乾燥しやすい
- 寝つきが悪い傾向
食習慣の傾向:
- 栄養が偏りやすい
- 食事を抜くことが多い
- 少食の傾向
体質タイプ別の食生活の考え方
体質タイプによって、適している食材や調理法、食べ方に傾向があります。ここでは、一般的な東洋医学の考え方として、参考になる情報をご紹介します。
気虚タイプに適した食材と調理法
気虚タイプには、消化しやすく、適度に「気」を補う食材が適していると考えられています。
参考になる食材例:
- 温かいスープや煮込み料理
- よく煮込んだ根菜類
- 消化の良い穀物(おかゆなど)
- 養分の豊富な食材(例:鶏肉、山芋)
調理法のポイント:
- 長時間煮込んで柔らかくする
- 一度に大量ではなく、少量を複数回
- 温かい状態で食べる
- よく噛んで食べる
気滞タイプの食習慣の調整ポイント
気滞タイプには、気の流れを促し、リラックスした状態で食事をすることが大切です。
参考になる食材例:
- 適度な苦味や香りのある野菜(セロリ、春菊など)
- 柑橘類
- 発酵食品(味噌、ぬか漬けなど)
食習慣のポイント:
- ゆっくり時間をかけて食べる
- 食事中はリラックスした環境を心がける
- よく噛んで食べる(30回以上が理想)
- 食後にゆっくり散歩するなど軽い運動を取り入れる
水滞タイプにおける食材選びの考え方
水滞タイプには、水分代謝をサポートする食材や調理法が参考になります。
参考になる食材例:
- 利尿作用があるとされる食材(ゴボウ、小豆など)
- 温かいお茶(ハト麦茶、ウーロン茶など)
- 水分の少ない調理法(焼く、炒めるなど)
食習慣のポイント:
- 冷たい飲み物は常温に近い温度で
- 夕食後の水分摂取を控えめに
- 塩分の取り過ぎに注意
- 温かい食事を中心に
血虚タイプと食事バランスの関係
血虚タイプには、栄養バランスの良い食事と規則正しい食習慣が大切です。
参考になる食材例:
- 鉄分を含む食材(レバー、ほうれん草、ひじきなど)
- タンパク質源(肉類、豆類など)
- 色の濃い野菜や果物(ニンジン、ブロッコリー、ブルーベリーなど)
食習慣のポイント:
- 食事を抜かない
- ゆっくり時間をかけて食べる
- 栄養バランスを意識する
- 就寝前の食事は避ける
体質に合わせた生活習慣の調整
食事内容だけでなく、食べ方や食事のタイミングも体質に合わせることで、より効果的に体調を整えることができると考えられています。
食事のタイミングと量の調整
東洋医学では「朝は王様のように、昼は貴族のように、夜は貧乏人のように食べる」という考え方があります。これは現代の栄養学でも支持される「朝食をしっかり、夕食は軽めに」という考え方に通じるものです。
体質別のポイント:
- 気虚タイプ:少量を複数回に分けて
- 気滞タイプ:ゆっくり時間をかけて、決まった時間に
- 水滞タイプ:夕食後の水分を控えめに
- 血虚タイプ:規則正しく栄養バランスを意識して
季節に合わせた体質ケアの知恵
東洋医学では、季節の変化に合わせて食材や調理法を調整することも大切と考えます。
季節別のポイント:
- 春:新陳代謝を促す軽い食事
- 夏:冷やしすぎない食事で水分代謝をサポート
- 秋:乾燥に備えて潤いを補う食材
- 冬:温かく消化の良い食事で体を温める
自分の体質を正確に知るには
セルフチェックの活用法と限界
ここでご紹介した内容を参考に、自分の体質の傾向を把握することはできますが、体質は複合的なものであり、また時期や環境によって変化することもあります。セルフチェックはあくまで参考程度にとどめておくのが良いでしょう。
専門家による体質診断の特徴
漢方の専門家による体質相談では、舌の状態、脈の状態、お腹の張り具合などを総合的に判断します。また、生活習慣や食事内容、心理状態なども含めた幅広い視点からアドバイスを受けることができます。
自分では気づかない体質の特徴や、複合的な体質タイプの場合など、専門家の目から見た客観的な評価を知ることで、より自分に合った養生法が見つかることもあります。
まとめ:自分に合った食生活で心身のバランスを整える
東洋医学の「体質」という考え方は、なぜ同じ食事法や生活習慣でも人によって結果が異なるのかを理解する上で参考になります。
自分の体質の特徴を知り、それに合った食習慣や生活リズムを取り入れることで、「無理なく続けられる」という大きなメリットが生まれます。
完璧を目指すのではなく、自分の体調や体質の変化に合わせて柔軟に調整していくことが、長期的に心地よい状態を保つコツかもしれません。
自分の体質についてもっと知りたい方は、ぜひ専門の漢方薬剤師に相談してみてください。一人ひとりの体質に合った、オーダーメイドのアドバイスを受けることができます。
あなたの体質タイプを知りたい方は銀座漢方天風堂薬局へ
専門の漢方薬剤師が、あなたの体質や症状に合わせた丁寧なアドバイスをお届けします。
あなた専用のオーダーメイド漢方相談
体質診断と食生活アドバイス
季節に合わせた養生法のご案内
LINE友達登録で漢方相談5,000円OFFクーポンをプレゼント!
※本記事は東洋医学の考え方を情報として提供するものであり、特定の効果・効能を保証するものではありません。体調に不安のある方は医療機関への受診をお勧めします。