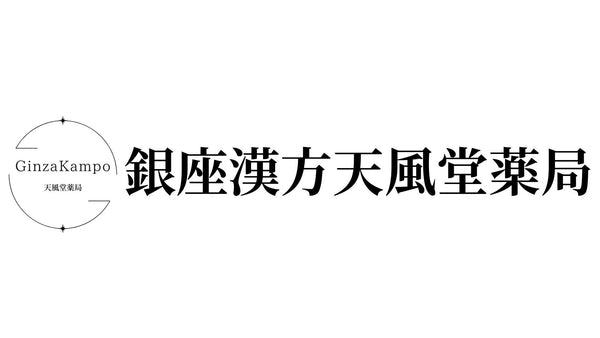監修:銀座漢方天風堂薬局 薬剤師 柳澤謙行(漢方薬剤師歴45年・日本東洋医学会会員)
朝と夜で体重が大きく変わる・・・
足のむくみが取れない・・・
靴がきつくなる・・・
このような悩みを抱えていませんか?
実は、体重変動やむくみは水分バランスと深い関係があります。東洋医学では、この現象を「水滞(すいたい)」という概念で捉えます。
この記事では、東洋医学の視点から、水分代謝の仕組みと日常生活での整え方について解説します。むくみや体重変動の悩みに対する新たな視点を得て、快適な毎日を過ごすヒントを見つけていただければ幸いです。
むくみと体重変動の仕組み
水分バランスが体に与える影響
健康な成人の体重の約60%は水分で構成されています。この体内の水分量は、日中の活動や食事、気温などさまざまな要因によって変動します。
1リットルの水分は約1kgの重さがあるため、水分の出入りが体重変動に大きく影響します。朝と夜で体重が1〜2kg変わるのは、主に水分によるものと考えられています。
体内の水分変動要因:
- 食事からの水分摂取(飲み物だけでなく食べ物にも含まれる)
- 排泄(尿、汗、呼吸など)による水分排出
- 塩分摂取による水分保持
- ホルモンバランスによる水分調整
- 重力の影響(立ち仕事で足にむくみが生じるなど)
東洋医学から見た「水滞」の考え方
東洋医学では、体内の水分代謝がスムーズでない状態を「水滞」と呼びます。これは現代医学で言う「むくみ」や「浮腫」に近い概念ですが、その捉え方には違いがあります。
水滞が生じる主な原因:
- 「気」の働きの低下(気虚)
- 「気」の流れの滞り(気滞)
- 「陽気」(温める力)の不足
- 過剰な水分・塩分の摂取
- 冷えによる水分代謝の低下
水滞が現れやすい部位:
- 下半身(特に足首や膝周り)
- 手指
- 顔(特に目の周り)
- お腹周り
- 全身(重だるさとして感じる場合も)
東洋医学では、水滞は単に水分量の問題だけでなく、「気・血・水」のバランスの乱れとして捉えます。特に「気」の働きが水分の巡りを促すと考えるため、水分代謝の改善には「気」の流れを整えることも重要とされています。
むくみやすさの体質的な特徴
「水滞」体質の特徴と傾向
東洋医学では、人によって水分代謝のしやすさに違いがあると考えます。「水滞」の傾向が強い方には、以下のような特徴が見られることがあります。
水滞体質の主な特徴:
- 朝と夜で体重変動が大きい(1kg以上)
- 指で皮膚を押すとへこみが残りやすい
- 湿度の高い時期に調子が悪くなる
- 塩分の多い食事の後にむくみやすい
- 水分をたくさん摂ると体がだるくなる
- 尿の量や回数が少ない傾向
これらの特徴は、あくまで東洋医学的な視点からの一般的な傾向です。医学的な診断ではないため、体調に不安がある場合は医療機関にご相談ください。
「気虚」と水分代謝の関係
東洋医学では、「気」(生命エネルギー)は水分を運ぶ働きも担っていると考えます。「気虚」(気の不足)の状態では、この水分を運ぶ力が弱まり、水滞が生じやすくなると考えられています。
気虚と水滞の関連する特徴:
- 疲れやすく、元気が出にくい
- 午後になると特にむくみやだるさを感じる
- 声が小さい、息切れしやすい
- 汗をかきやすいのに、むくみも生じる
- 長時間同じ姿勢でいるとむくみやすい
「冷え」とむくみの密接な関係
東洋医学では、体を温める「陽気」が水分代謝に重要な役割を果たすと考えます。体が冷えると水分の流れが滞りやすくなり、むくみの原因になるとされています。
冷えとむくみの悪循環:
冷えが生じると血行が悪くなり、水分代謝も低下します。すると水分が滞留して、さらに冷えを悪化させるという悪循環が生じることがあります。
冷えによるむくみの特徴:
- 冷たい部位にむくみが生じやすい
- 温めるとむくみが軽減する傾向
- 季節の変わり目や寒い時期に悪化
- 冷たい飲食物の摂取でむくみやすい
日常生活で意識したい水分代謝の考え方
適切な水分摂取のタイミングと量
水分摂取は健康維持に欠かせませんが、東洋医学では「いつ」「どのように」摂るかも重要と考えます。
水分摂取の工夫:
- 冷たい飲み物より常温や温かい飲み物を選ぶ
- 一度に大量ではなく、少量ずつこまめに摂る
- 就寝直前の大量の水分摂取は控える
- 喉が渇く前に水分補給する習慣を持つ
- 食事の直前・直後の大量の水分摂取を避ける
特に水滞の傾向がある方は、水分摂取の「質」にも注目することがポイントです。例えば、冷たい飲み物ではなく常温の飲み物を選ぶだけでも、体への負担が変わることがあります。
食事の選び方と調理法の工夫
東洋医学では、食材には水分代謝に関連する性質があると考えます。水滞の傾向がある方は、以下のような点を参考にしてみてください。
水分代謝に関連する食材例:
- 赤小豆、緑豆(古来より水分代謝に関連する食材として用いられてきた)
- ゴボウ、玄米、とうもろこし
- 冬瓜、きゅうり、スイカ(利尿作用があるとされる)
- 生姜、ネギ、にんにく(温性の食材)
調理法による違い:
- 水分の多い煮込み料理より、水分の少ない調理法(焼く、蒸す)を取り入れる
- 生食より温かく調理した食材が消化しやすい
- 香辛料や薬味を適度に活用する
- 塩分の取りすぎに注意する
生活習慣と姿勢の見直し
デスクワークや立ち仕事など、同じ姿勢を長時間続けることはむくみの原因になります。日常生活での小さな工夫が水分代謝を助けることがあります。
生活習慣の工夫:
- 1時間に一度は姿勢を変える、軽く体を動かす
- 足の位置を高くして休憩する時間を作る
- つま先の上げ下げなど、デスクでもできる簡単な運動を取り入れる
- 締め付けの強い服やベルトを避ける
- 就寝時は足を少し高くする工夫を取り入れる
季節別のむくみ対策の考え方
梅雨・夏場の湿気との付き合い方
湿度が高くなる時期は、体内の水分代謝も低下しやすくなります。特に梅雨から夏にかけては、むくみを感じやすい方が増える傾向があります。
梅雨・夏場のポイント:
- 室内の湿度管理に気を配る
- 冷たい飲み物の摂りすぎに注意
- 冷房による冷えを避ける工夫(腹巻、靴下など)
- 水分と一緒に適度な塩分補給も忘れずに
冬の冷えからくるむくみへの意識
冬は体が冷えやすく、水分代謝が滞りやすい季節です。冷えからくるむくみに対しては、温めることが基本となります。
冬場のポイント:
- 足元・腰回りの保温を意識する
- 温かい飲み物を選ぶ
- 入浴でしっかり体を温める
- 適度な運動で血行を促進する
「季節の変わり目は特に体調の変化に敏感になりましょう。東洋医学では、季節の特性に合わせた養生が大切と考えます。夏は湿邪(しつじゃ)、冬は寒邪(かんじゃ)という邪気が入りやすいとされ、それぞれに合わせた対策を取り入れることで、一年を通して快適な状態を保つことができます。」
—— 柳澤謙行 薬剤師(銀座漢方天風堂薬局)
東洋医学的な「巡り」を意識したセルフケア
身体を「温める」考え方
東洋医学では、体を温めることが水分代謝を促すために重要と考えます。特に、お腹・腰・足を温めることが基本とされています。
体を温める工夫:
- 腹巻や靴下で冷えやすい部位を保温する
- 温かい飲み物(生姜湯、ハーブティーなど)を取り入れる
- ぬるめのお湯(38〜40度)にゆっくり浸かる
- 冷えた状態での激しい運動を避ける
- 就寝前に足湯や半身浴で体を温める
「マッサージ」による水分循環の促進
東洋医学では、適切な刺激が気や血の流れを促し、結果として水分代謝も改善すると考えます。セルフマッサージは手軽に取り入れられる方法の一つです。
足のセルフマッサージの例:
- 足首から膝に向かって、やさしく押し上げるように撫でる
- 足の甲を親指で押し上げるように圧をかける
- 足の裏全体を親指でほぐす
- 指の間を軽くつまむように刺激する
※強く押しすぎず、痛みのない程度の力加減で行いましょう
東洋医学で水分に関連するツボ:
- 三陰交(さんいんこう):内くるぶしから指4本分上の位置
- 太渓(たいけい):内くるぶしとアキレス腱の間のくぼみ
- 湧泉(ゆうせん):足の裏、指を曲げた時にできるくぼみ
※これらのツボは東洋医学で水の巡りに関連するとされています
「動き」で巡りを良くする考え方
東洋医学では「動」と「静」のバランスを重視します。適度な活動と十分な休息が、気・血・水の巡りを整えると考えられています。
巡りを意識した動きの例:
- 朝のストレッチで一日の巡りを活性化
- ウォーキングなど負担の少ない有酸素運動
- 気功や太極拳などの東洋的な運動法
- 深い呼吸を意識した動き
- 入浴後のストレッチで血行促進
専門家に相談するタイミング
セルフケアだけでは難しいケース
むくみや体重変動は一時的なものであれば、セルフケアで対応できることも多いですが、以下のような場合は専門家への相談を検討してみましょう。
専門家に相談した方が良い例:
- むくみが長期間(数週間以上)続く場合
- 片側だけがむくむ場合
- 急に激しいむくみが生じた場合
- むくみと共に息切れや胸の痛みがある場合
- セルフケアを続けても改善が見られない場合
なお、体調に不安がある場合は、まず医療機関への受診をお勧めします。東洋医学的なアプローチは、西洋医学的な治療と併用することで、よりよい結果につながることもあります。
漢方相談での「水滞」評価の特徴
漢方の専門家による相談では、「水滞」について以下のような視点から総合的に評価します。
漢方相談での見立ての特徴:
- 舌の状態(色・形・苔の様子)
- 脈の状態(速さ・強さ・深さなど)
- 腹診(お腹の張り・温度・抵抗感など)
- 皮膚の状態(色・弾力・むくみなど)
- 生活習慣や食習慣の詳細な聞き取り
漢方相談のメリット:
- 体質に合わせた個別のアドバイス
- 生活習慣全体からの総合的な提案
- 西洋医学では見過ごされがちな微妙な変化への着目
- 長期的な視点からのアプローチ
まとめ:水分代謝を整えて快適な毎日を
むくみや体重変動に悩む多くの方にとって、東洋医学の「水滞」という考え方は新たな視点となるかもしれません。
水分代謝は、単に水の量を減らせばよいというものではなく、体全体のバランスや巡りの良さが大切です。無理な水分制限ではなく、適切な摂り方や生活習慣の工夫が、長期的には効果的なアプローチとなります。
季節の変化に合わせた調整や、日々の小さな習慣の積み重ねが、むくみの少ない快適な状態へと導いてくれるでしょう。
自分に合った水分バランスの整え方について、さらに詳しく知りたい方は、ぜひ漢方の専門家にご相談ください。一人ひとりの体質や生活スタイルに合わせた、オーダーメイドのアドバイスを受けることができます。
※本記事は東洋医学の考え方を情報として提供するものであり、特定の効果・効能を保証するものではありません。体調に不安のある方は医療機関への受診をお勧めします。