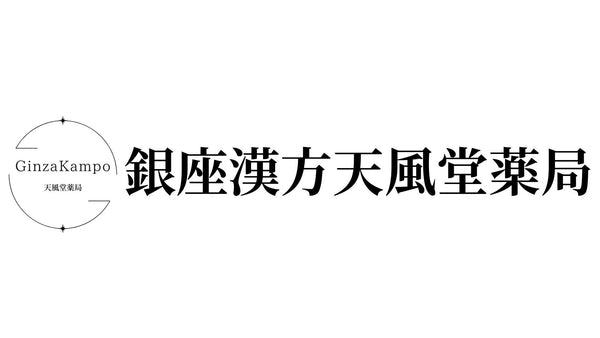監修:銀座漢方天風堂薬局 薬剤師 柳澤謙行(漢方薬剤師歴45年・日本東洋医学会会員)
「年齢とともに同じ食事量なのに太りやすくなった...」
「食べる量を減らしても体重が減らない...」
「代謝が落ちて体型が変わってきた...」
このような悩みを抱えている方は少なくありません。年齢を重ねるにつれて体質が変化し、若い頃と同じ食習慣では体型維持が難しくなることは珍しくありません。
この記事では、東洋医学の視点から「代謝」と「消化力」に着目し、「太りにくい体質づくり」について解説します。無理な食事制限ではなく、体質から考える持続可能なアプローチを見つけるヒントをご紹介します。
年齢とともに太りやすくなるメカニズム
西洋医学から見た加齢と代謝の関係
加齢による代謝の変化には、主に以下のような要因が関係しています:
- 筋肉量の減少: 30代以降、年間約1%ずつ筋肉量が減少すると言われています。筋肉は安静時でもエネルギーを消費する組織であるため、筋肉量の減少は基礎代謝の低下につながります。
- ホルモンバランスの変化: 女性は40代前後から始まる更年期に向けてエストロゲンの分泌が減少し、男性もテストステロンが徐々に減少します。これらのホルモン変化が脂肪の蓄積パターンや代謝に影響を与えます。
- 酵素活性の低下: 消化酵素の分泌量や活性が低下することで、食べたものをエネルギーに変換する効率が変化します。
東洋医学における「消化力」の考え方
東洋医学では、食べ物を消化・吸収し、エネルギーに変換する力を「脾胃(ひい)の働き」として重視します。
「脾胃」は現代の消化器系に近い概念ですが、単なる臓器ではなく、消化・吸収・運搬という一連の機能を司る重要な役割を担っています。この脾胃の働きが低下すると、食べ物がうまくエネルギーに変換されず、「痰湿(たんしつ)」と呼ばれる余分な水分や老廃物が体内に停滞しやすくなると考えられています。
加齢に伴い、「気」(生命エネルギー)の減少とともに脾胃の働きも弱まる傾向にあるため、同じ食事でも若い頃のようにはエネルギーに変換されにくくなるのです。
漢方で考える「太りやすさ」の体質的特徴
東洋医学では、太りやすさに関連する体質をいくつかのタイプに分類します。ご自身の傾向を知ることで、より効果的なアプローチが見えてくるかもしれません。
「脾虚」体質の特徴と傾向
脾虚は「脾の気が不足している」状態で、消化吸収力の低下が特徴です。
特徴的な傾向:
- 食後に胃もたれや膨満感を感じやすい
- 疲れやすく元気が出にくい
- 食べなくても太りやすい
- 朝が苦手で、午後になると元気が出る
- 冷たいものが苦手で、温かいものを好む
食習慣の傾向:
- 消化に時間がかかる
- 夕食が遅いと太りやすい
- 冷たい飲食物で調子を崩しやすい
「痰湿」体質の特徴と傾向
痰湿は水分代謝がスムーズでなく、体内に余分な水分や老廃物が停滞しやすい状態です。
特徴的な傾向:
- むくみやすい
- 体がだるく重く感じる
- べたつきやすい汗をかく
- 油っぽいものを食べると調子が悪くなる
- 湿度の高い季節に調子が悪くなる
食習慣の傾向:
- 脂っこいものや甘いものを好む傾向
- 水分の摂りすぎで調子を崩しやすい
- 食事量の多さより質が体型に影響する
「気滞」と代謝の関係
気滞は「気の流れが滞っている」状態で、ストレスや感情の変化が代謝に大きく影響します。
特徴的な傾向:
- ストレスがたまると食欲が増す
- 胸やみぞおちが張った感じがする
- イライラしやすく、気分の浮き沈みがある
- ストレスと体重増減が連動している
食習慣の傾向:
- 精神的なストレスで食べ過ぎる
- 早食いや不規則な食事が多い
- 緊張すると消化不良になりやすい
東洋医学から考える消化力を高める生活習慣
体質に合わせて日常生活を少し工夫することで、消化力や代謝を助けることができます。ここでは、東洋医学の視点からのアプローチをご紹介します。
「食べ方」の工夫と考え方
食べ方を意識することは、消化力を高める上で重要なポイントです。
基本的な考え方:
- よく噛んで食べる(一口30回以上が理想)
- 食事に集中し、テレビやスマホを見ながらの食事は避ける
- 適度な量を腹八分目で
- 規則正しい食事時間を心がける
- 立ったままや歩きながらの食事は避ける
東洋医学では「脾は思考を司る」とも考えられており、食事中に考え事や気を散らすことは、消化力を低下させると言われています。食事に集中することで、消化吸収を助けることができるのです。
「食べ合わせ」の東洋医学的視点
東洋医学では、食材には「性質」があると考えます。冷性・熱性・温性・涼性などの性質や、五味(甘・酸・苦・辛・鹹/しおからい)のバランスを意識することで、体質に合った食事選びができます。
体質別の食材選びの例:
- 脾虚タイプ:消化の良い食材(お粥、煮込み料理)、温性の食材(生姜、ネギ、シナモンなど)を取り入れる
- 痰湿タイプ:水分の少ない調理法(焼く、炒める)、苦味や香りのある食材(ゴーヤ、セロリなど)を意識する
- 気滞タイプ:気の巡りを促す食材(柑橘類、薬味など)、消化に良い調理法を選ぶ
「食べる量と頻度」のバランス
「いつ」「どのくらい」食べるかも重要なポイントです。東洋医学では「朝は王様のように、昼は貴族のように、夜は貧乏人のように食べる」という考え方があります。
体質別のポイント:
- 脾虚タイプ:一度に大量ではなく、少量を複数回に分けて
- 痰湿タイプ:夕食は軽めに、食後の水分は控えめに
- 気滞タイプ:ゆっくり時間をかけて、決まった時間に
代謝に関わる「巡り」を意識した生活習慣
東洋医学では「気血水の巡り」が代謝に大きく影響すると考えます。巡りを良くする生活習慣を取り入れることで、太りにくい体質づくりをサポートします。
「冷え」と代謝の密接な関係
冷えは代謝を低下させる大きな要因です。特に「腎陽虚」(腎の温める力の低下)は、加齢とともに生じやすくなります。
体を温める工夫:
- 腹巻や靴下で冷えやすい部位を保温する
- 温かい飲み物を選ぶ(白湯、生姜湯など)
- ぬるめのお湯(38〜40度)にゆっくり浸かる
- 冷えた状態での激しい運動を避ける
- 就寝前に足湯や半身浴で体を温める
「動き」が巡りに与える影響
適度な活動は気血の巡りを促し、代謝を高めます。激しい運動より、継続できる軽い運動が効果的です。
巡りを意識した活動例:
- 朝のストレッチで一日の巡りを活性化
- ウォーキングなど負担の少ない有酸素運動
- 気功や太極拳などの東洋的な運動法
- 深い呼吸を意識した動き
- 入浴後のストレッチで血行促進
「休息」の質と代謝の関連性
質の良い休息は代謝を整える上で欠かせません。特に睡眠は、ホルモンバランスや自律神経の調整に重要な役割を果たします。
質の良い休息のポイント:
- 22時〜2時の間はできるだけ睡眠を取る
- 就寝前のブルーライトを避ける
- 昼寝をするなら15〜20分程度に
- 深い呼吸でリラックスする時間を作る
- 過労を避け、適度な休息を取る
消化力と代謝に配慮した食事の基本的な考え方
体質に合わせた食材選びや調理法を工夫することで、消化力と代謝をサポートすることができます。
体を温める食材と調理法
体を温めることで代謝が高まります。特に寒い季節や冷え性の方は、温性の食材や調理法を意識すると良いでしょう。
温性の食材例:
- 生姜、ネギ、にんにく、シナモン
- 黒胡椒、八角、クローブなどのスパイス
- 羊肉、鶏肉、くるみなど
温める調理法:
- じっくり煮込む
- 蒸す
- 温かいスープや汁物として摂る
- 生で食べるより加熱調理する
消化を助けると考えられる薬味や香辛料
薬味や香辛料には消化を促進する働きがあると言われています。少量でも料理に取り入れることで、消化力をサポートできます。
消化を助ける薬味・香辛料例:
- 生姜(ショウガオール)
- 山椒(サンショオール)
- にんにく(アリシン)
- シナモン
- コリアンダー
- カレー粉(ターメリック含有)
季節に合わせた食材選びの知恵
東洋医学では、季節の変化に合わせて食材を選ぶことも大切だと考えます。自然の巡りに沿った食生活が、体内の巡りも整えると考えられています。
季節別の食材選び:
- 春:新鮮な若葉野菜、苦味のある食材(春菊、セリなど)
- 夏:水分の多い食材(きゅうり、トマトなど)、香りの強い食材(紫蘇など)
- 秋:根菜類、温性の食材を少しずつ増やす
- 冬:温性の食材、じっくり煮込んだ料理
体質別のアプローチの考え方
それぞれの体質特性に合わせたアプローチを取り入れることで、より効果的に太りにくい体質づくりができます。
「脾虚」タイプに適した生活習慣の工夫
脾虚タイプは消化力を高めることを中心に考えましょう。
生活習慣の工夫:
- 朝食はしっかり摂り、夕食は軽めに
- 消化の良い料理を選ぶ(長時間煮込んだスープなど)
- 冷たい飲食物は控え、温かいものを選ぶ
- 食後すぐの横になるのを避ける
- 適度な運動で気の巡りを促す
「痰湿」タイプの食生活のポイント
痰湿タイプは余分な水分や老廃物の排出を助ける工夫を取り入れましょう。
食生活のポイント:
- 甘いものや脂っこいものは控えめに
- 水分の摂りすぎに注意(特に夕食後)
- 温かい飲み物を選ぶ(ハト麦茶、ウーロン茶など)
- 苦味のある野菜を取り入れる
- 塩分の取りすぎに注意
「気滞」タイプのリラックス方法
気滞タイプはストレス管理と気の巡りを促す工夫がポイントです。
リラックス方法:
- 食事中はリラックスした環境を心がける
- 深い呼吸を意識する習慣を持つ
- 香りのよい食材(オレンジピールなど)を取り入れる
- 適度な運動で気の巡りを促す
- 自分なりのストレス発散法を見つける
専門家による体質診断の価値
自分の体質を正確に知ることは、効果的なアプローチの第一歩です。漢方の専門家による体質診断は、より的確な養生法を見つける助けになります。
セルフケアの限界と専門的アドバイスの意義
体質は複雑で多面的な要素を持っています。セルフチェックで大まかな傾向を知ることはできますが、専門家の視点からの評価も参考になります。
専門家診断のメリット:
- 複合的な体質の特定(多くの方は複数の体質特徴を持つ)
- 季節や環境による変化への対応方法
- 個別の生活習慣に合わせたアドバイス
- 経験豊富な視点からの総合的な評価
漢方相談でわかる自分の体質と傾向
漢方の専門家による相談では、舌・脈・腹などの状態から体質を総合的に判断します。
漢方相談の特徴:
- 舌の色や苔の状態の観察
- 脈の状態(速さ・強さ・特徴など)の確認
- お腹の状態(張り・温度など)の触診
- 詳細な問診(生活習慣・食習慣・睡眠など)
- 四診(望診・聞診・問診・切診)による総合判断
まとめ:体質を整えて太りにくい身体づくりを目指す
東洋医学では、「痩せる」ことよりも「体質を整える」ことに重点を置きます。体質が整うことで、結果として太りにくい身体へと変化していくのです。
「消化力」と「代謝」の観点から食習慣や生活習慣を見直すことで、無理なく続けられる体質改善のアプローチが見つかるでしょう。短期的な結果ではなく、長期的な心地よさを目指して、日々の小さな工夫を積み重ねていくことが大切です。
自分の体質や生活スタイルに合った方法を探るためには、専門家のアドバイスを受けることも一つの選択肢です。一人ひとりの体質に合ったオーダーメイドの養生法で、いきいきとした毎日を過ごしましょう。
※本記事は東洋医学の考え方を情報として提供するものであり、特定の効果・効能を保証するものではありません。体調に不安のある方は医療機関への受診をお勧めします。